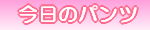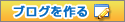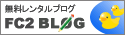あまり話さない話ですね~。
先日まで気分が滅入っていました。これも天気のせいかな??
台風21号が駆け抜け空は晴れていますがうちの近くの川にはまだ注意報が出ているようです。以前も書きましたが自分が小さい頃は某一級河川の上流近くに住んでいまして、奥には大きなダムがありました。ちなみに雷地方とも言われている地域でしたので夏から秋にかけて夕立が多くその都度、ダムの放流警報を聞いたものです。もう聞きなれたはずのサイレン音なのですが、あれを聞くとやっぱり不安になります。台風ともなれば茶色い濁流とともに流木が珍しくなく、大きな橋の下に溜まっていたりしました。あんな状態なのに魚がいなくならないのが不思議だと思ったものです。
ネットで10月の台風は珍しい、みたいな記事を読みました。でもまあ、来ないわけじゃないですよね。既に台風22号が発達しつつあるらしいですし。ただ季節的にまた日本をかすめるなんてことは少ないようなことも書いてありました。それで思い出したのが元寇。元軍の来襲は二回。一回目は文永の役で1274年の10月20日に博多湾に元軍900隻(と言われる)が現れて博多に上陸を開始。ちょうど今頃ですかねえ??大宰府守護の少弐氏が中心となり防衛戦を開始。しかし元軍の火薬を使った武器と集団戦法に一騎打ちだった鎌倉武士は大苦戦。博多湾から大宰府まで撤退し陣営を整えたところ翌21日。博多湾にいた元軍がすべて消えていました。「暴風が吹き荒れた」となっていますがこれには「諸説あり」なんですよね。
10月21日・・・今回の台風も10月後半だからきっと台風が・・・と思うかもしれませんが実は旧暦の10月21日。今の暦でいえばほぼほぼ12月(11月下旬)台風はちょっと考えられないとの事。ですので「この時は暴風はなかった」説も有力視されているそうです。またこの時の元軍の編成を見ると上陸して占領しようとするような編成ではないという見方があり「つまりこの攻撃は『脅し』と『強行偵察』(一度戦ってみてどの程度の戦力かを見る)でそもそも占領する気はなかった。だから一戦の勝利だけで帰っていったのだ」という説もあります。でもこの時の元軍が全滅していることも事実らしいので何かあったのは間違いないんでしょうけど・・・。確かNHK「北条時宗」(原作 高橋克彦)も『いつの間にか消えちゃった』説だったような。
二回目は弘安の役(1281年)。この時フビライは征東行省(東の征服を行う省)という役所まで設けて東つまり日本を占領する気マンマンだったらしいです。しかも先年に占領した南宋の軍も加えて兵力は14万。そうして博多湾に現れたのは7月29日頃。しかし30日の夜、暴風が吹き荒れ元軍を全滅させました。今度の「神風」はすべての資料に書かれているそうで間違いなく暴風が吹いた。今の暦でも8月下旬から9月上旬にあたり まさにシーズン。台風が来たんでしょうねえきっと。
やっぱ歴オタじみちゃいましたが台風の中、選挙がありました。かつてセールスマンが話題にしてはいけないこと「野球」「宗教」そして「政治」というのがありました。どれも微妙ですもんね。実家も商売をやっていたのでこれらには気を使っていました。けど実は父が某保守系政治家の後援会長でした(笑)ブログでもなるべく書かないようにはしてるつもりですが歴オタ崩れなので「宗教」そして「政治」はちと微妙に出てきますよねえ・・・。今回も元寇みたいな所があるような。。。元寇の時、日本の政治は「鎌倉幕府」という武士の政権、つまり軍事政権が担っていました。各地に守護がおり武芸を磨いていました。もしその時平安貴族の貴族政権だったら、怨霊が怖いので死刑を廃止するような、また健児の制程度の兵力だったら・・・歴史は変わってたかもしれないような(苦笑)
でも刀伊の入寇(1019年)は撃退してるんですけどね(笑)まー、それも武士のおかげですけど。しかもその後に防人復活!!(それも結局武士になるんですけど)
台風21号が駆け抜け空は晴れていますがうちの近くの川にはまだ注意報が出ているようです。以前も書きましたが自分が小さい頃は某一級河川の上流近くに住んでいまして、奥には大きなダムがありました。ちなみに雷地方とも言われている地域でしたので夏から秋にかけて夕立が多くその都度、ダムの放流警報を聞いたものです。もう聞きなれたはずのサイレン音なのですが、あれを聞くとやっぱり不安になります。台風ともなれば茶色い濁流とともに流木が珍しくなく、大きな橋の下に溜まっていたりしました。あんな状態なのに魚がいなくならないのが不思議だと思ったものです。
ネットで10月の台風は珍しい、みたいな記事を読みました。でもまあ、来ないわけじゃないですよね。既に台風22号が発達しつつあるらしいですし。ただ季節的にまた日本をかすめるなんてことは少ないようなことも書いてありました。それで思い出したのが元寇。元軍の来襲は二回。一回目は文永の役で1274年の10月20日に博多湾に元軍900隻(と言われる)が現れて博多に上陸を開始。ちょうど今頃ですかねえ??大宰府守護の少弐氏が中心となり防衛戦を開始。しかし元軍の火薬を使った武器と集団戦法に一騎打ちだった鎌倉武士は大苦戦。博多湾から大宰府まで撤退し陣営を整えたところ翌21日。博多湾にいた元軍がすべて消えていました。「暴風が吹き荒れた」となっていますがこれには「諸説あり」なんですよね。
10月21日・・・今回の台風も10月後半だからきっと台風が・・・と思うかもしれませんが実は旧暦の10月21日。今の暦でいえばほぼほぼ12月(11月下旬)台風はちょっと考えられないとの事。ですので「この時は暴風はなかった」説も有力視されているそうです。またこの時の元軍の編成を見ると上陸して占領しようとするような編成ではないという見方があり「つまりこの攻撃は『脅し』と『強行偵察』(一度戦ってみてどの程度の戦力かを見る)でそもそも占領する気はなかった。だから一戦の勝利だけで帰っていったのだ」という説もあります。でもこの時の元軍が全滅していることも事実らしいので何かあったのは間違いないんでしょうけど・・・。確かNHK「北条時宗」(原作 高橋克彦)も『いつの間にか消えちゃった』説だったような。
二回目は弘安の役(1281年)。この時フビライは征東行省(東の征服を行う省)という役所まで設けて東つまり日本を占領する気マンマンだったらしいです。しかも先年に占領した南宋の軍も加えて兵力は14万。そうして博多湾に現れたのは7月29日頃。しかし30日の夜、暴風が吹き荒れ元軍を全滅させました。今度の「神風」はすべての資料に書かれているそうで間違いなく暴風が吹いた。今の暦でも8月下旬から9月上旬にあたり まさにシーズン。台風が来たんでしょうねえきっと。
やっぱ歴オタじみちゃいましたが台風の中、選挙がありました。かつてセールスマンが話題にしてはいけないこと「野球」「宗教」そして「政治」というのがありました。どれも微妙ですもんね。実家も商売をやっていたのでこれらには気を使っていました。けど実は父が某保守系政治家の後援会長でした(笑)ブログでもなるべく書かないようにはしてるつもりですが歴オタ崩れなので「宗教」そして「政治」はちと微妙に出てきますよねえ・・・。今回も元寇みたいな所があるような。。。元寇の時、日本の政治は「鎌倉幕府」という武士の政権、つまり軍事政権が担っていました。各地に守護がおり武芸を磨いていました。もしその時平安貴族の貴族政権だったら、怨霊が怖いので死刑を廃止するような、また健児の制程度の兵力だったら・・・歴史は変わってたかもしれないような(苦笑)
でも刀伊の入寇(1019年)は撃退してるんですけどね(笑)まー、それも武士のおかげですけど。しかもその後に防人復活!!(それも結局武士になるんですけど)
突然ですが本を読みまして
定期通院してまいりました。心臓系の数値が良くなっていて驚き。でも体感は全くないんですけど(苦笑)
突然ですが、最近、ある本を読んで目のウロコと思った事があります。「何故 新選組ができたのか」です。
幕末、黒船来航、幕府独断?の通商条約締結により尊王攘夷論が高まり その上テロ事件 桜田門外の変を受けて 将軍徳川家茂(いえもち)は上洛し孝徳天皇に攘夷(外国人を打ち払う事)を奏上することになりました。将軍が上洛するのは徳川家光以来およそ230年ぶりの事。尊王論の高まり=将軍の失墜につながりますから、それだけ幕府の権威は落ちていたんですね。しかし京都所司代の武力だけでは道中また在京中の治安が維持できないとの清河八郎の建策により諸国の浪人から浪士隊が組まれ将軍護衛の任につくことになりました。
その浪士隊が紆余曲折後「京都守護職 会津藩主 松平容保」の預かりとなり「新選組」の名を賜りました。だけど…
「いやちょっとまてよ、徳川幕府は旗本8万騎と言われる大兵力を持ってるはず。そもそもなんで浪人で部隊を造らなきゃいけないの?旗本で組織すればいいじゃん」
そういえばそうですねえ。井伊家なんて武田家高坂氏の武門を受け継ぎ「井伊の赤備え」と言われたほどの武勇の家。しかもお役がない旗本衆がたくさんいるのに…なんで?
まずは旗本衆に遠征出来る程の資金がなかったという事があります。当時の旗本の財政は一部を除いて苦しいものでした。浪士隊編成の支度金は確か300両だったと思います。旗本が行くよりはるかに安上がりだったかも??しかし最大の理由は、当時の旗本はまさに官僚になり下がり「軍務」を行う事など不可能に近い者ばかりだった。刀は帯びていても腑抜けばっかだったという事でしょうか。しかしもちろん旗本が0だったわけではなく近習衆や大身の旗本は付き添いました。また京都警護にも「京都見廻組」という2旗本の隊が結成されてます。けど2隊で200名ほど。主に二条城の警備をしたと言いますがどう見ても少ないですよねえ。だって8万騎いる中の200人ですもん。(しかし坂本龍馬暗殺の首謀者という説あり)結局旗本衆だけではその役目が務まらず仕方なく浪人の出番と。死を賭して将軍の旗のもとに集ったのが浪人と言う皮肉。
そして京都の守備を担う軍事司令官も武勇に優れる譜代大名に命じられました。それが会津藩中将 松平容保。肩書も「京都守護職」という特別職。もし江戸初期に旗本でなく大名が「守護職」に選ばれたら「大名家に命じるなんて我ら旗本の恥」とか大騒ぎになっていたかもしれません。それこそ大久保彦左衛門 忠敬(ただたか)あたりが老中に直談判しに来たかも。彦左衛門なら「将軍様、天領を守るのは我ら旗本がお役。我らに命じられなければ腹を切る」とか言い出しそうですよね(苦笑)
これは長州の奇兵隊にも通じるものとか。奇兵隊も町人衆の集まりで相撲取りで集まった「力士隊」や呉服問屋が集まって「呉服隊」を組織したとか。やっぱ徳川300年の太平が「平和ボケ」を生んだんでしょうかねえ。
・・・なんか70年の太平を紡いだ現代にも通じてるような。。。当時の有名な狂歌は
泰平の眠りを覚ます上喜撰(じょうきせん) たつた四杯で夜も眠れず
上喜撰(じょうきせん)とは宇治茶の銘柄。これを浦賀沖に来たアメリカの蒸気船4隻に掛けたわけですね。たった4杯(隻)で夜も眠れない。当時もお茶を飲むと夜 眠れないと知れてたんですねえ。
幕末は4隻の黒船、現代はミサイル・・・になるんでしょうか。。。
突然ですが、最近、ある本を読んで目のウロコと思った事があります。「何故 新選組ができたのか」です。
幕末、黒船来航、幕府独断?の通商条約締結により尊王攘夷論が高まり その上テロ事件 桜田門外の変を受けて 将軍徳川家茂(いえもち)は上洛し孝徳天皇に攘夷(外国人を打ち払う事)を奏上することになりました。将軍が上洛するのは徳川家光以来およそ230年ぶりの事。尊王論の高まり=将軍の失墜につながりますから、それだけ幕府の権威は落ちていたんですね。しかし京都所司代の武力だけでは道中また在京中の治安が維持できないとの清河八郎の建策により諸国の浪人から浪士隊が組まれ将軍護衛の任につくことになりました。
その浪士隊が紆余曲折後「京都守護職 会津藩主 松平容保」の預かりとなり「新選組」の名を賜りました。だけど…
「いやちょっとまてよ、徳川幕府は旗本8万騎と言われる大兵力を持ってるはず。そもそもなんで浪人で部隊を造らなきゃいけないの?旗本で組織すればいいじゃん」
そういえばそうですねえ。井伊家なんて武田家高坂氏の武門を受け継ぎ「井伊の赤備え」と言われたほどの武勇の家。しかもお役がない旗本衆がたくさんいるのに…なんで?
まずは旗本衆に遠征出来る程の資金がなかったという事があります。当時の旗本の財政は一部を除いて苦しいものでした。浪士隊編成の支度金は確か300両だったと思います。旗本が行くよりはるかに安上がりだったかも??しかし最大の理由は、当時の旗本はまさに官僚になり下がり「軍務」を行う事など不可能に近い者ばかりだった。刀は帯びていても腑抜けばっかだったという事でしょうか。しかしもちろん旗本が0だったわけではなく近習衆や大身の旗本は付き添いました。また京都警護にも「京都見廻組」という2旗本の隊が結成されてます。けど2隊で200名ほど。主に二条城の警備をしたと言いますがどう見ても少ないですよねえ。だって8万騎いる中の200人ですもん。(しかし坂本龍馬暗殺の首謀者という説あり)結局旗本衆だけではその役目が務まらず仕方なく浪人の出番と。死を賭して将軍の旗のもとに集ったのが浪人と言う皮肉。
そして京都の守備を担う軍事司令官も武勇に優れる譜代大名に命じられました。それが会津藩中将 松平容保。肩書も「京都守護職」という特別職。もし江戸初期に旗本でなく大名が「守護職」に選ばれたら「大名家に命じるなんて我ら旗本の恥」とか大騒ぎになっていたかもしれません。それこそ大久保彦左衛門 忠敬(ただたか)あたりが老中に直談判しに来たかも。彦左衛門なら「将軍様、天領を守るのは我ら旗本がお役。我らに命じられなければ腹を切る」とか言い出しそうですよね(苦笑)
これは長州の奇兵隊にも通じるものとか。奇兵隊も町人衆の集まりで相撲取りで集まった「力士隊」や呉服問屋が集まって「呉服隊」を組織したとか。やっぱ徳川300年の太平が「平和ボケ」を生んだんでしょうかねえ。
・・・なんか70年の太平を紡いだ現代にも通じてるような。。。当時の有名な狂歌は
泰平の眠りを覚ます上喜撰(じょうきせん) たつた四杯で夜も眠れず
上喜撰(じょうきせん)とは宇治茶の銘柄。これを浦賀沖に来たアメリカの蒸気船4隻に掛けたわけですね。たった4杯(隻)で夜も眠れない。当時もお茶を飲むと夜 眠れないと知れてたんですねえ。
幕末は4隻の黒船、現代はミサイル・・・になるんでしょうか。。。
清すぎる水は・・・魚も住めない?後編
定期健診の眼底検査に行ってまいりました。
眼底検査が年々(自分は半年ごとですが)簡単になっていくような気がします。最初の頃は目にレンズを入れて診たのですが、半年前は外側からレンズを使って覗くのみ。今回は通常使ってる検眼器具で普通にみて「異常なし」・・・。う~ん、なんとなく釈然としませんがカルテには以前の具合が書かれてる事でしょうからこの程度で良いと判断されたのでしょうか。それに6ヶ月検診で結構頻繁ですしね。。。
前回の続き
一番 ちと・・・なんだかなあ~?と思うのは個人的には寛政の改革の松平定信です~。
松平定信は吉宗の孫になります。定信直前の為政者は老中 田沼意次(おきつぐ)。昔は「田沼の政治」と言えば賄賂が横行する悪い政治と習いました。田沼意次はそれこそ時代劇に出てくる悪代官そのもののイメージ。ですが、これはすべて松平定信のイメージ戦略だったとの最近の説があります。確かに付け届けや現代なら賄賂に近い物もあったのですが、それは江戸時代の慣習法でもあり田沼が特に悪い事をしたという事実は無いようです。実は田沼意次は経済眼がすごくあり有能な人だった。江戸時代と言えば石高制。武士のお給料は米で払われる。でも米は食べ物であるから売ってお金に変えなければならない。この米を買う商人を札差と言い、実はお米は札差に買いたたかれていました。そりゃそうで、たくさん出回れば安くなってしまうのは道理です。ならば高い時に売ればよいのですがそういう事は「武士はしないもの」だったらしい。泣く泣く安値で売ってたのでしょうかねえ。。。
武士の困窮はこの「米給料制度」が原因と考え、田沼意次は貫高制にしようとしてたらしいです。貫高制と言えば戦国時代初期の制度。簡単に言えば土地から取れるお米を銭に換算するものです。つまりこれからはお給料を米ではなく銭で払おうというのです。こうすればお米は幕府の方で高い時に放出する、とか色々出来て幕府の財政も潤うと考えていたそうです。そして貨幣改鋳。お金の金銀の含有量を減らし、減らした金銀を使い新しくお金を多くつくって幕府の財源にする。そして結局はそのお金が市中にばら撒かれる。これは今でいうお金を刷ってお金の供給量を増やす政策。「黒田バズーカ」の江戸版ですね。つまり流通する貨幣量を増やしデフレを解消する政策でした。言ってみれば重農政策に対して重商政策を行おうとしてました。
しかしこういう考えが松平定信は大嫌いでした。
なんでかと言うと、一番は「祖の法を崩す」 祖先が考えた法律を変えることは儒教において大罪だというわけです。また士農工商と言う身分でもわかる通り、金もうけとは汚い行為と見ていたんだそうです。「商は詐なり」(商売とは騙すことだ)儒教に反するそんな事を幕府がするなんてもっての外じゃ~!!そういう意味で松平定信は田沼意次が大っ嫌いでした。田沼意次の悪事(ほとんどが冤罪)を流布したのは定信だったとも言われる所以です。意次の息子 意知(おきとも)は「悪事の報いで」暗殺されますが、これも松平定信のさしがね説があります。
お上の政策はすべて「金権政治の田沼が悪い」と流布されていた江戸庶民は この暗殺を聞いて大喜びしたとか。意次は息子の死に落胆したのか、その後すぐに失脚します。これには天明の大飢饉直後の政治の混乱という理由もありますが、やっぱり松平定信の謀事だそうです。この田沼意次に剣術指南役として重用されていたのが秋山小平。池波正太郎「剣客商売」の主人公です。池波正太郎はまだまだ田沼意次が「悪徳政治家」と思われていたであろう時代に 既に先見の明を持った有能な政治家(老中)であったと描いています。たぶん、こっちが正しいんじゃないかなあ、と思います。
田沼の失脚後、田沼色をすべて払拭するため松平定信は動き出します。田沼から取り上げた領地に建っていた城は破却。それは礎石まで掘り出して打ち捨てるという念の入れよう。そして「昔に帰れ」とばかりに寛政の改革を行いました。それは庶民から楽しみを奪う「清い改革」でまたまた重農政策。貨幣改鋳は元に戻され市中に出回る金銀が減少、再びデフレ化させる事になってしまいました。この時代を映す有名な狂歌がありますよね。
白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき
(松平定信は白河藩主)
白河の水(政治)が清すぎて魚(庶民)は住みにくい、濁っていた田や沼(田沼政治)が恋しい、戻りたい。
「水清くして魚住まず」を地でいってる狂歌ですねえ(苦笑)もしかして、この狂歌が語源かしらん???
ただ松平定信は地元白河では名君で通っていたそうです。一番は天明の大飢饉の時、自領白河藩の飢えにうまく対処したこと。ただ飢饉で苦しむ他国からコメを自国だけに集めたとかいう説もあります。またこの飢饉直後だったので重農政策、贅沢禁止になりやすかったことなどの理由はありますが・・・やっぱやりすぎな「清い」政治家という評価でしょうねえ。。。
振り返れば現在、衆議院の選挙ですけど、「清い」とか「改革」とか耳触りの良い言葉には注意が必要なのかもしれませんねえ。。。
PS ちなみに池波正太郎「鬼平犯科帳」もこの時代の作品。主人公の鬼平こと長谷川平蔵 宣以(のぶため)も「白河公は清廉すぎる」と言うようなことを小説の中で言ってるんですよね。ドラマだと上司は若年寄 京極備前守。多分 松平定信は出てないんじゃないかと思うんです。一応全作観てますが・・・出てこなかったような。。。
眼底検査が年々(自分は半年ごとですが)簡単になっていくような気がします。最初の頃は目にレンズを入れて診たのですが、半年前は外側からレンズを使って覗くのみ。今回は通常使ってる検眼器具で普通にみて「異常なし」・・・。う~ん、なんとなく釈然としませんがカルテには以前の具合が書かれてる事でしょうからこの程度で良いと判断されたのでしょうか。それに6ヶ月検診で結構頻繁ですしね。。。
前回の続き
一番 ちと・・・なんだかなあ~?と思うのは個人的には寛政の改革の松平定信です~。
松平定信は吉宗の孫になります。定信直前の為政者は老中 田沼意次(おきつぐ)。昔は「田沼の政治」と言えば賄賂が横行する悪い政治と習いました。田沼意次はそれこそ時代劇に出てくる悪代官そのもののイメージ。ですが、これはすべて松平定信のイメージ戦略だったとの最近の説があります。確かに付け届けや現代なら賄賂に近い物もあったのですが、それは江戸時代の慣習法でもあり田沼が特に悪い事をしたという事実は無いようです。実は田沼意次は経済眼がすごくあり有能な人だった。江戸時代と言えば石高制。武士のお給料は米で払われる。でも米は食べ物であるから売ってお金に変えなければならない。この米を買う商人を札差と言い、実はお米は札差に買いたたかれていました。そりゃそうで、たくさん出回れば安くなってしまうのは道理です。ならば高い時に売ればよいのですがそういう事は「武士はしないもの」だったらしい。泣く泣く安値で売ってたのでしょうかねえ。。。
武士の困窮はこの「米給料制度」が原因と考え、田沼意次は貫高制にしようとしてたらしいです。貫高制と言えば戦国時代初期の制度。簡単に言えば土地から取れるお米を銭に換算するものです。つまりこれからはお給料を米ではなく銭で払おうというのです。こうすればお米は幕府の方で高い時に放出する、とか色々出来て幕府の財政も潤うと考えていたそうです。そして貨幣改鋳。お金の金銀の含有量を減らし、減らした金銀を使い新しくお金を多くつくって幕府の財源にする。そして結局はそのお金が市中にばら撒かれる。これは今でいうお金を刷ってお金の供給量を増やす政策。「黒田バズーカ」の江戸版ですね。つまり流通する貨幣量を増やしデフレを解消する政策でした。言ってみれば重農政策に対して重商政策を行おうとしてました。
しかしこういう考えが松平定信は大嫌いでした。
なんでかと言うと、一番は「祖の法を崩す」 祖先が考えた法律を変えることは儒教において大罪だというわけです。また士農工商と言う身分でもわかる通り、金もうけとは汚い行為と見ていたんだそうです。「商は詐なり」(商売とは騙すことだ)儒教に反するそんな事を幕府がするなんてもっての外じゃ~!!そういう意味で松平定信は田沼意次が大っ嫌いでした。田沼意次の悪事(ほとんどが冤罪)を流布したのは定信だったとも言われる所以です。意次の息子 意知(おきとも)は「悪事の報いで」暗殺されますが、これも松平定信のさしがね説があります。
お上の政策はすべて「金権政治の田沼が悪い」と流布されていた江戸庶民は この暗殺を聞いて大喜びしたとか。意次は息子の死に落胆したのか、その後すぐに失脚します。これには天明の大飢饉直後の政治の混乱という理由もありますが、やっぱり松平定信の謀事だそうです。この田沼意次に剣術指南役として重用されていたのが秋山小平。池波正太郎「剣客商売」の主人公です。池波正太郎はまだまだ田沼意次が「悪徳政治家」と思われていたであろう時代に 既に先見の明を持った有能な政治家(老中)であったと描いています。たぶん、こっちが正しいんじゃないかなあ、と思います。
田沼の失脚後、田沼色をすべて払拭するため松平定信は動き出します。田沼から取り上げた領地に建っていた城は破却。それは礎石まで掘り出して打ち捨てるという念の入れよう。そして「昔に帰れ」とばかりに寛政の改革を行いました。それは庶民から楽しみを奪う「清い改革」でまたまた重農政策。貨幣改鋳は元に戻され市中に出回る金銀が減少、再びデフレ化させる事になってしまいました。この時代を映す有名な狂歌がありますよね。
白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき
(松平定信は白河藩主)
白河の水(政治)が清すぎて魚(庶民)は住みにくい、濁っていた田や沼(田沼政治)が恋しい、戻りたい。
「水清くして魚住まず」を地でいってる狂歌ですねえ(苦笑)もしかして、この狂歌が語源かしらん???
ただ松平定信は地元白河では名君で通っていたそうです。一番は天明の大飢饉の時、自領白河藩の飢えにうまく対処したこと。ただ飢饉で苦しむ他国からコメを自国だけに集めたとかいう説もあります。またこの飢饉直後だったので重農政策、贅沢禁止になりやすかったことなどの理由はありますが・・・やっぱやりすぎな「清い」政治家という評価でしょうねえ。。。
振り返れば現在、衆議院の選挙ですけど、「清い」とか「改革」とか耳触りの良い言葉には注意が必要なのかもしれませんねえ。。。
PS ちなみに池波正太郎「鬼平犯科帳」もこの時代の作品。主人公の鬼平こと長谷川平蔵 宣以(のぶため)も「白河公は清廉すぎる」と言うようなことを小説の中で言ってるんですよね。ドラマだと上司は若年寄 京極備前守。多分 松平定信は出てないんじゃないかと思うんです。一応全作観てますが・・・出てこなかったような。。。
清すぎる水は・・・魚も住めない?前編
病院へ行ってまいりました。先日検査した足の腫れの検査結果を聞きに。結果は・・・「原因不明」
また違う病院へ行くことに。。。足が悪いのにまた遠くへ行くんか~~い!と言っても仕方ありません。このままでは靴が履きにくいしその中の靴下も履きにくい、というより脱ぎにくい。脱ぐとクッキリ跡が残るほど浮腫んでるんですよねえ。。。
今やだれでも知ってることでしょうが、江戸時代の3大改革は全て失敗でした。というより改悪と言っても良いものでした。江戸の3大改革とは
享保の改革1716 徳川吉宗
寛政の改革1787 松平定信
天保の改革1841 水野忠邦
自分たちエロ漫画に関して一番影響受けたのは最後の天保の改革でしょうかねえ。確かこの改革から「読み物にみだらな描画はまかりならぬ」というお触れが出て、以来ず~~~とあそこにはスミベタになりました(江戸にスミベタがあったかどうかわかんないですけど(笑))要するに猥褻物として性器を描いてはならぬの原点がここでしょうね、きっと。(間違ってたら ごめんなさい)
今や有名になりましたが江戸時代の3大改革は「改革」とは名ばかりの「改悪」でした。共通する理念は「昔へ帰れ」儒教が流布しきったからでしょうかねえ??と、いうより儒教の最もわるい部分を凝縮させたと言ってもいい「朱子学」を心棒する指導者によって行われたというのが正しいのかも知れません。「朱子学」は以前書いたと思いますが南宋時代の人、朱熹(しゅき)が唱えた新しい儒教の考えです。英語でもNeo-Confucianism(新儒教)と訳される事もあります。が、すごく後ろ向きな考え方です。儒教そのものが「孝」を最高徳目としてるように「古い事」=「正しい」という理念を持ってますが、朱子学はもっと極端だと言います。
時代背景として漢民族の中華(中原を支配する最高の国)である宋が 北方の野蛮人の国 金(女真族、後の満州民族)や元(モンゴル)に負けてしまった。「いや、違うんだ。奴らは武力で国を奪った野蛮な覇王だ。本当は徳を持っている我々 漢民族が正統な王者なのだ」極端に言えばこういう思いが思想になったのが朱子学だと言います。つまり負けているという現実を見ないで「ホントはこっちが正統なんだぞ。だから俺たちの方が偉いんだ!!それを認めろ~」俺が正統だ論ですねえ。これは現代でもどこかの国の行動がちょっとそっくりかな?と思えたり。。。
ともかく江戸3大改革は「祖先の決めた法」と「重農主義」を推し進めるものでした。結果 新しく生まれた価値観や民衆の思いを弾圧してしまいました。すべての改革時代には せっかく花開いた民衆文化がしぼんでしまいます。心中話で有名な近松門左衛門は享保の改革(徳川吉宗)の時代の人ですけど「心中物語は不届きである」として禁止にされてしまいした。ま~、当時心中が増えていたらしいからチョッと仕方ないかなとも思うけど それだけでなく歌舞音曲は縮小、色街も華美な衣装や音曲は咎められ、贅沢品は禁止。おかげで職人は職にあぶれていきます。高いものはダメだから安いものばっか出回る。職人や料理人も安いものしか売れないから儲からない…。これって今で言うデフレですよねえ。。。吉宗というと貧乏人の為の「医療院」とか「目安箱」を設置して民衆の声を聞いたというイメージですが 実はその改革のほとんどが倹約政策と農業回顧政策だったそうです。能力主義を取り入れたのも有名で南町奉行 大岡越前がその代表ですが、後々すこ~しヤバイ方向に。何故なら江戸時代通じて最も農民を苦しめた非情な代官は吉宗の時代に現れたそうです。つまり「能力がある」から農民から沢山「むしり取った」わけですね。しかも吉宗のお気に入り…。ま、有能には違いないんだろうけど…ねえ。。。
現代でもお上が考える「有能」と下々が考える「有能」にはやっぱ差があるようですしねえ。ある動画を観ていたら某省で「有能」とされるのは「税を上げる政策を提案する人」であり「景気や国民所得を上げる政策を提案する人」はあまり評価されないんだとか。景気や国民所得が上がれば結果 税収が必然的に上るんじゃないかと思うのですが手っ取り早く「取る」方が評価されるんですねえ、やっぱり。ま、その動画を観た限りのお話ですが(苦笑)
また違う病院へ行くことに。。。足が悪いのにまた遠くへ行くんか~~い!と言っても仕方ありません。このままでは靴が履きにくいしその中の靴下も履きにくい、というより脱ぎにくい。脱ぐとクッキリ跡が残るほど浮腫んでるんですよねえ。。。
今やだれでも知ってることでしょうが、江戸時代の3大改革は全て失敗でした。というより改悪と言っても良いものでした。江戸の3大改革とは
享保の改革1716 徳川吉宗
寛政の改革1787 松平定信
天保の改革1841 水野忠邦
自分たちエロ漫画に関して一番影響受けたのは最後の天保の改革でしょうかねえ。確かこの改革から「読み物にみだらな描画はまかりならぬ」というお触れが出て、以来ず~~~とあそこにはスミベタになりました(江戸にスミベタがあったかどうかわかんないですけど(笑))要するに猥褻物として性器を描いてはならぬの原点がここでしょうね、きっと。(間違ってたら ごめんなさい)
今や有名になりましたが江戸時代の3大改革は「改革」とは名ばかりの「改悪」でした。共通する理念は「昔へ帰れ」儒教が流布しきったからでしょうかねえ??と、いうより儒教の最もわるい部分を凝縮させたと言ってもいい「朱子学」を心棒する指導者によって行われたというのが正しいのかも知れません。「朱子学」は以前書いたと思いますが南宋時代の人、朱熹(しゅき)が唱えた新しい儒教の考えです。英語でもNeo-Confucianism(新儒教)と訳される事もあります。が、すごく後ろ向きな考え方です。儒教そのものが「孝」を最高徳目としてるように「古い事」=「正しい」という理念を持ってますが、朱子学はもっと極端だと言います。
時代背景として漢民族の中華(中原を支配する最高の国)である宋が 北方の野蛮人の国 金(女真族、後の満州民族)や元(モンゴル)に負けてしまった。「いや、違うんだ。奴らは武力で国を奪った野蛮な覇王だ。本当は徳を持っている我々 漢民族が正統な王者なのだ」極端に言えばこういう思いが思想になったのが朱子学だと言います。つまり負けているという現実を見ないで「ホントはこっちが正統なんだぞ。だから俺たちの方が偉いんだ!!それを認めろ~」俺が正統だ論ですねえ。これは現代でもどこかの国の行動がちょっとそっくりかな?と思えたり。。。
ともかく江戸3大改革は「祖先の決めた法」と「重農主義」を推し進めるものでした。結果 新しく生まれた価値観や民衆の思いを弾圧してしまいました。すべての改革時代には せっかく花開いた民衆文化がしぼんでしまいます。心中話で有名な近松門左衛門は享保の改革(徳川吉宗)の時代の人ですけど「心中物語は不届きである」として禁止にされてしまいした。ま~、当時心中が増えていたらしいからチョッと仕方ないかなとも思うけど それだけでなく歌舞音曲は縮小、色街も華美な衣装や音曲は咎められ、贅沢品は禁止。おかげで職人は職にあぶれていきます。高いものはダメだから安いものばっか出回る。職人や料理人も安いものしか売れないから儲からない…。これって今で言うデフレですよねえ。。。吉宗というと貧乏人の為の「医療院」とか「目安箱」を設置して民衆の声を聞いたというイメージですが 実はその改革のほとんどが倹約政策と農業回顧政策だったそうです。能力主義を取り入れたのも有名で南町奉行 大岡越前がその代表ですが、後々すこ~しヤバイ方向に。何故なら江戸時代通じて最も農民を苦しめた非情な代官は吉宗の時代に現れたそうです。つまり「能力がある」から農民から沢山「むしり取った」わけですね。しかも吉宗のお気に入り…。ま、有能には違いないんだろうけど…ねえ。。。
現代でもお上が考える「有能」と下々が考える「有能」にはやっぱ差があるようですしねえ。ある動画を観ていたら某省で「有能」とされるのは「税を上げる政策を提案する人」であり「景気や国民所得を上げる政策を提案する人」はあまり評価されないんだとか。景気や国民所得が上がれば結果 税収が必然的に上るんじゃないかと思うのですが手っ取り早く「取る」方が評価されるんですねえ、やっぱり。ま、その動画を観た限りのお話ですが(苦笑)
神が在っても神無月
10月に入りました。
10月の別名「神無月」各地の神が出雲大社に出向くため「神がいなくなる月」だから「神無月」となったと昔 教わりました。が、「大語源」によるとむしろ「神な月」(神の月)から「神無月」になったという全く逆の説。これは6月を「水な月」(水の月)=「水無月」というのと同じ。出雲地方では神が集まってくるから「神在月」と言うのですがこれも本当は俗信なのだそうです。
10月は収穫祭や田の神が山の神に戻ったりと確かに神様がお忙しい月。出雲に出向いていられませんね。ちなみになんで神様が出雲大社に出向くかと言えば祀られている大国主との会議が目的。神様 皆んなで相談し今後の運命や人の生き死にを決定するんだそうです。でも昔はなんで出雲なの?日本の最高神、天照大御神の伊勢神宮じゃないの?と思ってました。が、日本の神は一神教と違い、役割がはっきり別れます。これはギリシャ神話とかでもそうですが死の神が生き物の運命(死)を司どり決定してるのです。ギリシャ神話や北欧神話では死の神が実は「他の神の死」も左右していたりするんですよねえ。場合によっては最高神ですらその決定に従わなければならなかったりします。大国主もそういう神様なんです。現世(うつしよ)を天照大御神が統治し、大国主はあの世(幽世=かくりよ)死を司る神になりました。そして日本的なところはそれでも「死=運命」を「神様皆で」決めるところ。・・・というかこれは大国主の動向を皆で監視するためなのかもしれません。なにせ大国主は古事記では須佐之男命の6世の孫(日本書紀では息子)・・・実はタタリ神なのです。
・・・とまあ、自分の勝手な解釈なわけですが(笑)大国主命はなんだか特殊な神様なんじゃないのかしらん?とは昔から思っていました。そんな神様にちなむ月・・・災い転じて福となる・・・はず!!
10月の別名「神無月」各地の神が出雲大社に出向くため「神がいなくなる月」だから「神無月」となったと昔 教わりました。が、「大語源」によるとむしろ「神な月」(神の月)から「神無月」になったという全く逆の説。これは6月を「水な月」(水の月)=「水無月」というのと同じ。出雲地方では神が集まってくるから「神在月」と言うのですがこれも本当は俗信なのだそうです。
10月は収穫祭や田の神が山の神に戻ったりと確かに神様がお忙しい月。出雲に出向いていられませんね。ちなみになんで神様が出雲大社に出向くかと言えば祀られている大国主との会議が目的。神様 皆んなで相談し今後の運命や人の生き死にを決定するんだそうです。でも昔はなんで出雲なの?日本の最高神、天照大御神の伊勢神宮じゃないの?と思ってました。が、日本の神は一神教と違い、役割がはっきり別れます。これはギリシャ神話とかでもそうですが死の神が生き物の運命(死)を司どり決定してるのです。ギリシャ神話や北欧神話では死の神が実は「他の神の死」も左右していたりするんですよねえ。場合によっては最高神ですらその決定に従わなければならなかったりします。大国主もそういう神様なんです。現世(うつしよ)を天照大御神が統治し、大国主はあの世(幽世=かくりよ)死を司る神になりました。そして日本的なところはそれでも「死=運命」を「神様皆で」決めるところ。・・・というかこれは大国主の動向を皆で監視するためなのかもしれません。なにせ大国主は古事記では須佐之男命の6世の孫(日本書紀では息子)・・・実はタタリ神なのです。
・・・とまあ、自分の勝手な解釈なわけですが(笑)大国主命はなんだか特殊な神様なんじゃないのかしらん?とは昔から思っていました。そんな神様にちなむ月・・・災い転じて福となる・・・はず!!