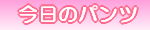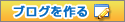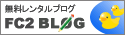ガンダムを見ましたPart2
もう先々月になる?のことですが前回のMSイグルーの続編、MSイグルー重力戦線を観ました。
前回はジオン軍の話、今回は連邦軍の話です。
ーーーー以下、ネタバレがありますーーーー
以前どこかで地球連邦軍の元ネタ?はソビエト連邦軍というのを見た気がします。そういえば制服の襟とか階級賞のつき方とかなんとなく旧ソビエト軍っぽいような。(官僚の弊害が大きいみたいなところとかも)
しかしこの第一話の連邦軍は第二次世界大戦中のアメリカ軍っぽい雰囲気。映画で言えば「プライベート・ライアン」ゲームでは「メダル・オブ・オナー」の様な。まだ連邦軍にはモビルスーツが無くジオンのザクが圧倒的な威力を誇っていた時の物語。この時代のザクはある意味超兵器で連邦軍は虎の子の?戦車部隊を守るため直接戦闘はさせずにザクに対抗するのは歩兵部隊という設定です。一番の感想は歩兵からみた「ザク」ってなんて怖いんだ!!ということです。劇中でも「一つ目の巨人」と言っていますがまさに「キュプロス」・・・怖すぎです。18mの巨体で追っかけてこられたらビビリまくりです。。。その上に 歩兵相手にザクマシンガンぶっぱなしてくるわ、ヒートホークで切りかかってくるわ。。。ソンムで初めて戦車の突撃を目にしたドイツ兵もこんな恐怖だったのでしょうか。でもソンムでの戦車は極初期のものだからスピードはゆっくりだし初めはびっくりしたでしょうが、結局ドイツ軍の野砲でやられてしまったというのも読みました。やっぱりザクの比ではなさそうですね。このザクは連邦軍の撤退路上に孤立してしまっていて、ザク側としても援軍はこないしどうしようもない状態なのですが、このザクのおかげで連邦軍は組織だった撤退ができないという設定っぽいです。この設定見て思い出したのは小林原文さんの「街道上の怪物」でしょうか。独ソ戦がはじまった初期にドイツ軍の補給路上にソ連軍のKV-1重戦車が一台 各座してしまった。当時のドイツ軍の戦車や対戦車砲では破壊できず、この動けないたった一台の戦車のためにドイツ軍の攻勢が止まってしまった・・・という物語です。結局ドイツ軍は排除のため大掛かりな囮の戦車を出し、88mm高射砲の水平射撃使って仕留めるという展開になるのですが、こちらの連邦軍では派遣したのは歩兵二個中隊だけ・・・。この第一話はやっぱり「ザクの恐怖」だと思いました。「ザクって怖い」です。
第二話は「陸の王者」連邦軍61式戦車の話。この作品の連邦軍(戦車部隊)は一転してなんとな~くイギリス軍っぽい雰囲気に(赤いベレー帽が)61式戦車といえば、ゲーム「ギレンの野望」シリーズではとにかく大量生産して数で対抗するという兵器でした。しかも3スタックくらいぶつけてもザクの部隊を破壊できないというヤラレメカの代表のような悲しい存在です。しかしこの作品の61戦車はものすごくかっこいい。というより逆に61戦車ってこんなかっこよくなるんだぁと。戦車で連装砲ってどうよと思っていたのですがこの作品見ると ところがどっこい、まさに劇中のセリフ「連装砲ってのはこう使うんだ!!」という具合にかっこいいです。ほんとうにリアルな感じに。CGはすごいですねぇ。ヤラレメカのイメージ払拭間違いなしという感じでした。
ストーリーはジオン軍のザクにやられ片足を失った戦車兵がその復讐を果たそうする話。カタキのザクは全身を白色に塗られたエース機で「ホワイトオーガ」という異名をもつ。復讐に執着するあまり部隊からは浮き上がり孤立している。そこへ配属された新任の操縦兵(主人公)の目を通して語られる「戦士の執念」の物語。
このストーリーのモチーフはやっぱり「白鯨」でしょうか。戦車長はエイハブ船長、そこへ赴任してくる操縦兵はイシュメルにあたりますでしょうか。「ホワイト・オーガ」はまさに白鯨「モビーディック」。「ホワイトオーガ」に対する敵対心は「モビーディック」を悪魔的に憎悪するエイハブ船長に似ているように思いますし、その憎悪のおかげで周りの人間も巻き込み 死に追いやってしまうという所なんかも・・・。
ーーーー以下「白鯨」のネタバレにもなりますがーーーー「白鯨」とは日本近海で最後の死闘を行います。エイハブ船長は自ら打ち込んだ銛のロープに巻き取られ白鯨によって海のそこに引きずり込まれてしまう。白鯨の体にくくりつけられてしまったエイハブ船長の腕が波に洗われ左右に動くさまを捕鯨船から見た乗組員が「みろ、俺はもうだめだ(死んでいる)って言ってるぜ」というシーンが印象的でした。この映画を観たのはかなり子供の頃だったのですけど。。。「白鯨」では捕鯨船の乗組員はイシュメル一人だけを残してすべて死んでしまいますが、この作品も新任の操縦兵を残し小隊は全滅してしまいます。やっぱり「一人の巨大な執念(憎悪)が周りにも地獄をもたらす」ということなのでしょうか。(「白鯨」はアメリカ文学の代表としてよく映画なんかに出てきます。「エイハブは正しい」という肯定的な解釈もあるようです)
第三話は連邦軍の大反抗作戦「オデッサ作戦」の話。
連邦軍もすでにモビルスーツを開発ずみで「陸戦ジム」を大量に投入してきます。しかしジオン軍の陸上戦艦「ダブテ」の砲撃に苦戦を強いられている。。。このダブテってゲームではそんなに凶悪なユニットではないんですけど。確かに硬いのですが砲撃は命中率が低いし。。。ジオンの防衛網を突破して後方のダブテを攻撃するのに「強襲型ガンタンク」が出てきます。この兵器の小隊を指揮するのは作中初の女性主人公。(前作のモニカ・キャディラック大尉はやっぱりヒロインだと思いますし)このガンタンク、むちゃくちゃ強いです。前作のジオン版ガンタンク「ヒルドルブ」の比ではないかも。なにせ「強襲型」ですからキャラキャラと進むのろいガンタンクのイメージではありません。ロケットへ兵器のごときスピードを誇ります。ザクをなぎ倒しドムすらも倒して戦線を突破しダブテの元に。しかしこのむちゃくちゃ強いガンタンクは開発中止となっています。それは主人公の元彼が実はジオンのスパイでこのガンタンクの情報を漏らした為。主人公は同罪にとられ投獄されてしまう。このガンタンクへの搭乗もある意味懲罰的なものなのでしょうか。目標のダブテには裏切った元彼が乗っていてその復讐のために視野が狭くなっていると言う状態。だけど漏洩したとはいえこんな強いガンタンクを生産しないのはちょっともったいないような。このオデッサ作戦までガンタンク部隊は各地を転戦していたようです。なんとな~くドイツ軍の突撃砲部隊のような使われ方なのかなあと。見た目も似てますしね。ロケットへ兵器と書きましたがこの作戦はロケット機「桜花」のごとき特攻作戦です。その執念は自分を裏切った元彼への憎悪なのでしょうか・・・(このあたりの展開は個人的にはかなり微妙なんですけど)。。。実はこの裏には別の真実も隠されているのですが。。。ふと小学生の頃初めて作った戦車のプラモデルを思い出しました。タミヤの「ロンメル」。実は「ロンメル」はあだ名で正式には「ヤークト・パンター(ハンティング・パンサー)」箱にロンメル将軍が好んで使っていたから・・・という様なことが書かれていました。でもこれはどうやらタミヤの創作らしくそんな呼ばれ方はされていなかったらしいです。なんでニックネームつけたのかよく解かりませんねえ「ハンティング・パンサー」じゃ長かったから??(でも「ハンティング・タイガー」というプラモはあったし)
このMSイグルー重力戦線三話とも部隊は共通しています。冷徹な中佐が本当にいやな上官としていい味だしています。それよりもなによりも最大の共通存在は「死神」です。主人公たちはこの「死神に魅入られた」人々という解釈になっています。三者三様ですが共通の死神(女)にとり憑かれて死んでいく・・・。ちょっと他の人の感想を2,3みたのですけど、どうもこの「死神」、不評のようです。確かにガンダムというSF?の世界に死神という超常的存在は違和感あるという意見も解かる気がします。「死神がなければもっと良い」みたいな感想も読みましたし。わかる・・・のですがでもあの死神の存在はあれでいいかもと思うところもあります。多分「死神」と言う存在に 戦士の魂をバルハラ(北欧神話の大神オーディンの宮殿)に連れて行くという「ワルキューレ」とかけてあるのだろう(だからこの死神は女なのでしょう)と思うと神話好きな自分はいいかもなと感じてしまったりするんですよね。。。
ーーーーーーーー
以上、ちょっとうろ覚えなので間違っていたらすみません。
追伸・・・となるのでしょうか。炭水化物ダイエットを行いちょっと痩せました。もし55kg当時に仮に5kg痩せたら大変なことですが、現在の体重ではそれが10kgでも「焼け石に水」です(それでもまだ0.1トン強・・・)それに炭水化物の量は減っていますが食べる全体の量は減ってないですし。。。
前回はジオン軍の話、今回は連邦軍の話です。
ーーーー以下、ネタバレがありますーーーー
以前どこかで地球連邦軍の元ネタ?はソビエト連邦軍というのを見た気がします。そういえば制服の襟とか階級賞のつき方とかなんとなく旧ソビエト軍っぽいような。(官僚の弊害が大きいみたいなところとかも)
しかしこの第一話の連邦軍は第二次世界大戦中のアメリカ軍っぽい雰囲気。映画で言えば「プライベート・ライアン」ゲームでは「メダル・オブ・オナー」の様な。まだ連邦軍にはモビルスーツが無くジオンのザクが圧倒的な威力を誇っていた時の物語。この時代のザクはある意味超兵器で連邦軍は虎の子の?戦車部隊を守るため直接戦闘はさせずにザクに対抗するのは歩兵部隊という設定です。一番の感想は歩兵からみた「ザク」ってなんて怖いんだ!!ということです。劇中でも「一つ目の巨人」と言っていますがまさに「キュプロス」・・・怖すぎです。18mの巨体で追っかけてこられたらビビリまくりです。。。その上に 歩兵相手にザクマシンガンぶっぱなしてくるわ、ヒートホークで切りかかってくるわ。。。ソンムで初めて戦車の突撃を目にしたドイツ兵もこんな恐怖だったのでしょうか。でもソンムでの戦車は極初期のものだからスピードはゆっくりだし初めはびっくりしたでしょうが、結局ドイツ軍の野砲でやられてしまったというのも読みました。やっぱりザクの比ではなさそうですね。このザクは連邦軍の撤退路上に孤立してしまっていて、ザク側としても援軍はこないしどうしようもない状態なのですが、このザクのおかげで連邦軍は組織だった撤退ができないという設定っぽいです。この設定見て思い出したのは小林原文さんの「街道上の怪物」でしょうか。独ソ戦がはじまった初期にドイツ軍の補給路上にソ連軍のKV-1重戦車が一台 各座してしまった。当時のドイツ軍の戦車や対戦車砲では破壊できず、この動けないたった一台の戦車のためにドイツ軍の攻勢が止まってしまった・・・という物語です。結局ドイツ軍は排除のため大掛かりな囮の戦車を出し、88mm高射砲の水平射撃使って仕留めるという展開になるのですが、こちらの連邦軍では派遣したのは歩兵二個中隊だけ・・・。この第一話はやっぱり「ザクの恐怖」だと思いました。「ザクって怖い」です。
第二話は「陸の王者」連邦軍61式戦車の話。この作品の連邦軍(戦車部隊)は一転してなんとな~くイギリス軍っぽい雰囲気に(赤いベレー帽が)61式戦車といえば、ゲーム「ギレンの野望」シリーズではとにかく大量生産して数で対抗するという兵器でした。しかも3スタックくらいぶつけてもザクの部隊を破壊できないというヤラレメカの代表のような悲しい存在です。しかしこの作品の61戦車はものすごくかっこいい。というより逆に61戦車ってこんなかっこよくなるんだぁと。戦車で連装砲ってどうよと思っていたのですがこの作品見ると ところがどっこい、まさに劇中のセリフ「連装砲ってのはこう使うんだ!!」という具合にかっこいいです。ほんとうにリアルな感じに。CGはすごいですねぇ。ヤラレメカのイメージ払拭間違いなしという感じでした。
ストーリーはジオン軍のザクにやられ片足を失った戦車兵がその復讐を果たそうする話。カタキのザクは全身を白色に塗られたエース機で「ホワイトオーガ」という異名をもつ。復讐に執着するあまり部隊からは浮き上がり孤立している。そこへ配属された新任の操縦兵(主人公)の目を通して語られる「戦士の執念」の物語。
このストーリーのモチーフはやっぱり「白鯨」でしょうか。戦車長はエイハブ船長、そこへ赴任してくる操縦兵はイシュメルにあたりますでしょうか。「ホワイト・オーガ」はまさに白鯨「モビーディック」。「ホワイトオーガ」に対する敵対心は「モビーディック」を悪魔的に憎悪するエイハブ船長に似ているように思いますし、その憎悪のおかげで周りの人間も巻き込み 死に追いやってしまうという所なんかも・・・。
ーーーー以下「白鯨」のネタバレにもなりますがーーーー「白鯨」とは日本近海で最後の死闘を行います。エイハブ船長は自ら打ち込んだ銛のロープに巻き取られ白鯨によって海のそこに引きずり込まれてしまう。白鯨の体にくくりつけられてしまったエイハブ船長の腕が波に洗われ左右に動くさまを捕鯨船から見た乗組員が「みろ、俺はもうだめだ(死んでいる)って言ってるぜ」というシーンが印象的でした。この映画を観たのはかなり子供の頃だったのですけど。。。「白鯨」では捕鯨船の乗組員はイシュメル一人だけを残してすべて死んでしまいますが、この作品も新任の操縦兵を残し小隊は全滅してしまいます。やっぱり「一人の巨大な執念(憎悪)が周りにも地獄をもたらす」ということなのでしょうか。(「白鯨」はアメリカ文学の代表としてよく映画なんかに出てきます。「エイハブは正しい」という肯定的な解釈もあるようです)
第三話は連邦軍の大反抗作戦「オデッサ作戦」の話。
連邦軍もすでにモビルスーツを開発ずみで「陸戦ジム」を大量に投入してきます。しかしジオン軍の陸上戦艦「ダブテ」の砲撃に苦戦を強いられている。。。このダブテってゲームではそんなに凶悪なユニットではないんですけど。確かに硬いのですが砲撃は命中率が低いし。。。ジオンの防衛網を突破して後方のダブテを攻撃するのに「強襲型ガンタンク」が出てきます。この兵器の小隊を指揮するのは作中初の女性主人公。(前作のモニカ・キャディラック大尉はやっぱりヒロインだと思いますし)このガンタンク、むちゃくちゃ強いです。前作のジオン版ガンタンク「ヒルドルブ」の比ではないかも。なにせ「強襲型」ですからキャラキャラと進むのろいガンタンクのイメージではありません。ロケットへ兵器のごときスピードを誇ります。ザクをなぎ倒しドムすらも倒して戦線を突破しダブテの元に。しかしこのむちゃくちゃ強いガンタンクは開発中止となっています。それは主人公の元彼が実はジオンのスパイでこのガンタンクの情報を漏らした為。主人公は同罪にとられ投獄されてしまう。このガンタンクへの搭乗もある意味懲罰的なものなのでしょうか。目標のダブテには裏切った元彼が乗っていてその復讐のために視野が狭くなっていると言う状態。だけど漏洩したとはいえこんな強いガンタンクを生産しないのはちょっともったいないような。このオデッサ作戦までガンタンク部隊は各地を転戦していたようです。なんとな~くドイツ軍の突撃砲部隊のような使われ方なのかなあと。見た目も似てますしね。ロケットへ兵器と書きましたがこの作戦はロケット機「桜花」のごとき特攻作戦です。その執念は自分を裏切った元彼への憎悪なのでしょうか・・・(このあたりの展開は個人的にはかなり微妙なんですけど)。。。実はこの裏には別の真実も隠されているのですが。。。ふと小学生の頃初めて作った戦車のプラモデルを思い出しました。タミヤの「ロンメル」。実は「ロンメル」はあだ名で正式には「ヤークト・パンター(ハンティング・パンサー)」箱にロンメル将軍が好んで使っていたから・・・という様なことが書かれていました。でもこれはどうやらタミヤの創作らしくそんな呼ばれ方はされていなかったらしいです。なんでニックネームつけたのかよく解かりませんねえ「ハンティング・パンサー」じゃ長かったから??(でも「ハンティング・タイガー」というプラモはあったし)
このMSイグルー重力戦線三話とも部隊は共通しています。冷徹な中佐が本当にいやな上官としていい味だしています。それよりもなによりも最大の共通存在は「死神」です。主人公たちはこの「死神に魅入られた」人々という解釈になっています。三者三様ですが共通の死神(女)にとり憑かれて死んでいく・・・。ちょっと他の人の感想を2,3みたのですけど、どうもこの「死神」、不評のようです。確かにガンダムというSF?の世界に死神という超常的存在は違和感あるという意見も解かる気がします。「死神がなければもっと良い」みたいな感想も読みましたし。わかる・・・のですがでもあの死神の存在はあれでいいかもと思うところもあります。多分「死神」と言う存在に 戦士の魂をバルハラ(北欧神話の大神オーディンの宮殿)に連れて行くという「ワルキューレ」とかけてあるのだろう(だからこの死神は女なのでしょう)と思うと神話好きな自分はいいかもなと感じてしまったりするんですよね。。。
ーーーーーーーー
以上、ちょっとうろ覚えなので間違っていたらすみません。
追伸・・・となるのでしょうか。炭水化物ダイエットを行いちょっと痩せました。もし55kg当時に仮に5kg痩せたら大変なことですが、現在の体重ではそれが10kgでも「焼け石に水」です(それでもまだ0.1トン強・・・)それに炭水化物の量は減っていますが食べる全体の量は減ってないですし。。。
「ソプラノズ」を観ましたpart1
「ソプラノズ」を観ました。
レンタル店になかったので古い海外ドラマで値段も安いですしアマゾンで購入。内容は「現代マフィアの経営と苦悩」というところでしょうか。もちろんテーマは「家族愛」。
ーーーーー以下、内容に触れます(ネタバレあり)ーーーーー
主人公はニュージャージーでファミリー(一家)を抱えるトニー・ソプラノ。マフィアのボスである。ある日バーベキュー・パーティで原因不明の失神をする。体に不調はなく原因は精神的なもの「パニック発作」と診断されイヤイヤながら精神分析医を受診することに。トニーはファミリーの経営や頑固な叔父ジュニアの横暴、家庭では妻の小言と長女の大学進学、そして全ての事に不満をもつ母リヴィアの対応に悩まされる日々だった。
初めは精神分析を馬鹿ににした態度をとっていたトニー。しかしマフィアのボスで巨漢のトニーを恐れることなく親身に話をきく女医メルフィのセラピーに段々と心を開いていく。トニーの鬱の遠因には人格障害である母親リヴィアの影があることが見えてきた・・・
DVDシーズン1のパッケージには「マフィアのボスは、悩めるパパだった・・・。」という宣伝文句がありますが、そんな感じの内容はシーズン1が一番でシーズンが2,3と進むと殺伐とした、いかにもマフィアのドラマっぽくなっていきます。また私は普通吹き替えで観るのですがシーズン1だけ声優が全部違っています。シーズン1では主人公トニーを渡瀬恒彦がやっていますがシーズン2以降は池田勝というように。。。女医メルフィにいたってはシーズン1、2,3とも声優が違うのでなんか微妙に違和感が。メルフィは多分トニーと同年輩だと思うのですがシーズン2の声はちょっと若すぎなような気がしました(でも個人的にはシーズン2の声が一番セクシーで好きです)主人公の声も渡瀬恒彦のトニーは物静かな雰囲気、池田勝のトニーはほんとにヤクザな感じという感想です。何かしら事情があったのでしょうがやっぱり統一してもらったほうがいいように思いました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ちょっと古めのドラマなのでコンパクトDVDになっていてお値段もお手頃。ですのでシーズン5まで買いました。でもシーズン6(ラストシーズン)だけはまだコンパクトDVD化されていなくてちょっと高いんです。あんまりお金のない私はコンパクト化されるまで待っています。う~ん、でも早く観たい。先をしりたくないので感想など見ないようにしているのですが、なにやらラストは賛否両論だそうです。。。早くみたい。コンパクト化まだかな。。。
レンタル店になかったので古い海外ドラマで値段も安いですしアマゾンで購入。内容は「現代マフィアの経営と苦悩」というところでしょうか。もちろんテーマは「家族愛」。
ーーーーー以下、内容に触れます(ネタバレあり)ーーーーー
主人公はニュージャージーでファミリー(一家)を抱えるトニー・ソプラノ。マフィアのボスである。ある日バーベキュー・パーティで原因不明の失神をする。体に不調はなく原因は精神的なもの「パニック発作」と診断されイヤイヤながら精神分析医を受診することに。トニーはファミリーの経営や頑固な叔父ジュニアの横暴、家庭では妻の小言と長女の大学進学、そして全ての事に不満をもつ母リヴィアの対応に悩まされる日々だった。
初めは精神分析を馬鹿ににした態度をとっていたトニー。しかしマフィアのボスで巨漢のトニーを恐れることなく親身に話をきく女医メルフィのセラピーに段々と心を開いていく。トニーの鬱の遠因には人格障害である母親リヴィアの影があることが見えてきた・・・
DVDシーズン1のパッケージには「マフィアのボスは、悩めるパパだった・・・。」という宣伝文句がありますが、そんな感じの内容はシーズン1が一番でシーズンが2,3と進むと殺伐とした、いかにもマフィアのドラマっぽくなっていきます。また私は普通吹き替えで観るのですがシーズン1だけ声優が全部違っています。シーズン1では主人公トニーを渡瀬恒彦がやっていますがシーズン2以降は池田勝というように。。。女医メルフィにいたってはシーズン1、2,3とも声優が違うのでなんか微妙に違和感が。メルフィは多分トニーと同年輩だと思うのですがシーズン2の声はちょっと若すぎなような気がしました(でも個人的にはシーズン2の声が一番セクシーで好きです)主人公の声も渡瀬恒彦のトニーは物静かな雰囲気、池田勝のトニーはほんとにヤクザな感じという感想です。何かしら事情があったのでしょうがやっぱり統一してもらったほうがいいように思いました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ちょっと古めのドラマなのでコンパクトDVDになっていてお値段もお手頃。ですのでシーズン5まで買いました。でもシーズン6(ラストシーズン)だけはまだコンパクトDVD化されていなくてちょっと高いんです。あんまりお金のない私はコンパクト化されるまで待っています。う~ん、でも早く観たい。先をしりたくないので感想など見ないようにしているのですが、なにやらラストは賛否両論だそうです。。。早くみたい。コンパクト化まだかな。。。
「世界の怪人」辞典を読みました。
文庫本「世界の怪人」辞典読みました。
知らない怪人もいて面白かったのですが、怪人のくくり?がイマイチ微妙なような気がしました。例えば第一章「神秘の怪人」「神や悪魔と対等に渡り合った」となっていて「ソロモン」や「ゴリアテ」「マーリン」などですが、そこに「卑弥呼」や「諸葛孔明」、「ネロ」が入っています。・・・微妙なような。。。「神話時代から5、6世紀ぐらいまで」というくくりなのですが「神話時代」(神話や伝説)と「実証可能時代」(歴史書に出てくる人)に分けたほうがよいかもしれないなあと・・・。私「三国志」には詳しくないので間違っていたらすみませんが、現在流布している「三国志」は「三国志演義」という読み物(歴史から作られているが架空の物語)だというのを読んだことがあります。「忠臣蔵」と同じでしょうか。「赤穂事件」から作られた「忠臣蔵」という架空の物語のデキが良過ぎて「忠臣蔵」が史実の物語と思われているとも。(原作「忠臣蔵」は室町時代の話になっている)もし諸葛孔明の事跡が「三国志演義」によっているものだとすると「神話時代」(神話や伝説)にはいってもいいのかなとも思いました。三国志は詳しくないので本当に間違っていたらすみません。。。第二章も「神秘の怪人」となっています。この中に「役小角」「ジル・ド・レイ」「ファウスト」「アグリッパ」・・・「風魔小太郎」や「天草四郎」など。 キリスト教系とその他に分けたほうがよかったかもと。「陰陽道と修験道」ともなっていますがこのくくりなら陰陽道から「阿倍仲麻呂」や「吉備真備」も入れても良かったような気もしました。それに地獄の書記だったという「小野篁(おののたかむら)」がこの本に載っていなかったことは少し残念。でも面白かったと思います。「怪人」というくくりで一冊の本を作るのは大変だったのかSFや架空の怪人も網羅されていました。「ドラキュラ」「怪人二十面相」「アルセーヌ・ルパン」や「貞子」「ジグソウ」、「ジェイソン」とか「ブギーマン」。ここでもちょっと思ったのですが「映画13日の金曜日から ジェイソン」となっているのに「映画ハロウィンから ブギーマン」となっています。これなら「映画ハロウィンから マイケル・マイヤーズ」じゃないのかなぁ?ハロウィンは2までしか観ていないので後のシリーズは犯人がマイケルじゃないのかな?
色々書きましたが、私にとってこの怪人の本は面白かったしためにもなりました。サンジェルマン伯とかジーン・ディクソン、鉄仮面など、よく知りませんでした。
知らない怪人もいて面白かったのですが、怪人のくくり?がイマイチ微妙なような気がしました。例えば第一章「神秘の怪人」「神や悪魔と対等に渡り合った」となっていて「ソロモン」や「ゴリアテ」「マーリン」などですが、そこに「卑弥呼」や「諸葛孔明」、「ネロ」が入っています。・・・微妙なような。。。「神話時代から5、6世紀ぐらいまで」というくくりなのですが「神話時代」(神話や伝説)と「実証可能時代」(歴史書に出てくる人)に分けたほうがよいかもしれないなあと・・・。私「三国志」には詳しくないので間違っていたらすみませんが、現在流布している「三国志」は「三国志演義」という読み物(歴史から作られているが架空の物語)だというのを読んだことがあります。「忠臣蔵」と同じでしょうか。「赤穂事件」から作られた「忠臣蔵」という架空の物語のデキが良過ぎて「忠臣蔵」が史実の物語と思われているとも。(原作「忠臣蔵」は室町時代の話になっている)もし諸葛孔明の事跡が「三国志演義」によっているものだとすると「神話時代」(神話や伝説)にはいってもいいのかなとも思いました。三国志は詳しくないので本当に間違っていたらすみません。。。第二章も「神秘の怪人」となっています。この中に「役小角」「ジル・ド・レイ」「ファウスト」「アグリッパ」・・・「風魔小太郎」や「天草四郎」など。 キリスト教系とその他に分けたほうがよかったかもと。「陰陽道と修験道」ともなっていますがこのくくりなら陰陽道から「阿倍仲麻呂」や「吉備真備」も入れても良かったような気もしました。それに地獄の書記だったという「小野篁(おののたかむら)」がこの本に載っていなかったことは少し残念。でも面白かったと思います。「怪人」というくくりで一冊の本を作るのは大変だったのかSFや架空の怪人も網羅されていました。「ドラキュラ」「怪人二十面相」「アルセーヌ・ルパン」や「貞子」「ジグソウ」、「ジェイソン」とか「ブギーマン」。ここでもちょっと思ったのですが「映画13日の金曜日から ジェイソン」となっているのに「映画ハロウィンから ブギーマン」となっています。これなら「映画ハロウィンから マイケル・マイヤーズ」じゃないのかなぁ?ハロウィンは2までしか観ていないので後のシリーズは犯人がマイケルじゃないのかな?
色々書きましたが、私にとってこの怪人の本は面白かったしためにもなりました。サンジェルマン伯とかジーン・ディクソン、鉄仮面など、よく知りませんでした。
「デクスター シーズン4」を見ました
「デクスター」のシーズン4を見ました。
お気に入りの海外ドラマ、シーズン4が出ていたことに気づきませんでした。以前書きましたがマイアミ警察の「血痕専門鑑識官」のデクスターが実は連続殺人犯というドラマです。テーマは「家族愛」アメリカのドラマでは基本ですね。(というよりアメリカのドラマはほぼ家族愛がテーマ)殺人鬼デクスターは心を失っているが恋人リタとその家族と付き合うことで、そして結婚し本当の家族となり良き父親を演じることで心を取り返し始める?という物語になるのでしょうか。
ーーーー以下以前のシリーズ含めネタばれがありますーーーー
シリアルキラー(連続殺人犯)の多くは幼少期に虐待を受けていることが多く人格障害の原因でもあるとも言います。ロバート・K・レスラー「FBI心理捜査官」の内容のうろ覚えなので間違ってたらすみません(汗)この本は実際にFBI心理捜査官だった作者の実録なだけに迫力がありました。当時話題になったので読んだ方も多いかと思います。
ちょっと話が変わりますが、本来なら愛されるべき親から虐待を受けると「虐待を受けているのは自分ではない、別の人物なのだ」と別人格を作ってしまうことがある。これがいわゆる多重人格(解離性同一性障害)漫画やドラマだと二重人格が多いですが人格が二人だけという事は稀で多数の人格がある場合がほとんどらしい(漫画で多数の人格を表現するのは難しそうですしね)これは当時ベストセラーになったダニエル・キイスの「24人のビリー・ミリガン」からです。実在の多重人格者の記録になるのでしょうか。ちょうど「FBI心理捜査官」が流行ってたころで続けて読んだ気がします。その流れでロバート・D・ヘラーの「診断名サイコパス」も読みました。あのころは自分の中で異常心理学?がマイブーム(死後)で「平気でうそをつく人たちー虚偽と邪悪の心理学」古本で福島章「犯罪心理学」も読みました。まあ、ほぼ内容を忘れてしまってますけど・・・・(笑)「平気でうそをつく人たち」はベストセラーになっていたので読んだ方も多いと思います。平易な訳文で読みやすかった分 内容はけっこう考えさせられました。 こういった心理学書系を読むと他人を心理学的にあてはめてしまうことがあります。しかしこれらの本でも書かれていましたが、一知半解の知識で人を判断しようとすることは危険な事だと注意をうながしていました。ちょうど家庭の医学を読んだ時と同じでしょうか。家庭の医学を読むと過敏になり、ちょっとしたことが病気の原因になっているようで怖くなったりしますから。通ってた学校の表現関係の先生に言わせると「心理学は苦手」だそうで。理由は「心に方程式をあてはめるようだから」とのこと。たしかにそういう考え方もあるのかもしれないなあと思いました。仮にみんなフロイト流に判断したらエロエロな世界になりそうですしね(完全に素人考えなんですけど)
このデクスターも通説通り?幼少期のトラウマを抱えています。
元薬中毒で密告屋の母親がチェーンソーで切り殺される所を目撃、三日間その血の海に実の兄とともに閉じ込められていたという。(デクスター自身はそのおぞましい記憶を封印して忘れてしまっている)そんなデクスターを発見し、養子に向かえ、さらに理解し導いたのは優秀な警察官であった義父のハリー・モーガンだった。危険な性質になってしまったデクスターに「闇の衝動(殺しの衝動)」の処理の仕方?を仕込んだ。「殺しの衝動が起こったら、殺されてもいい人間を殺せ。」つまり殺人鬼デクスターの標的は「殺人犯」。主に法を逃れて社会に隠れている殺人犯が標的となる。厳しい掟が決められていて標的が本当に殺人犯であるとわかったときでないと殺すことはできない。ある種正義の殺人鬼それがデクスター。デクスターは義父ハリーの教えに従い鑑識官になったが、ハリーの本当の娘(デクスターの義理の妹)デボラも父と同じ道に進み刑事になる。この奔放で下品な?義妹デボラへの愛情(といっても家族としての愛)も物語の鍵。
トラウマのため忘れていたデクスターの実の兄も その後別の施設で生活を送り成長してから 連続殺人犯「冷凍者キラー」として彼の前に現れる。これがシーズン1でした。デクスターは泣く泣く殺人鬼となった兄を殺す。シーズン2ではデクスターの過去の犠牲者の遺体が発見され「殺人鬼ベイハーバー・ブッチャー」事件となってしまう。そこへ放火魔のライラという女性もからんで事件になる。シーズン3では名前つきの殺人鬼はいませんが今回のシーズン4では「トリニティ」という殺人鬼が現れます。
アメリカ各地で連続した殺人事件が起こる。最初はバスタブで若い女性の全裸死体。次に中年女性の墜落死体。最後は中年男性の撲殺死体。必ずこの順番で3死体が出るがFBIでは自殺や通り魔として処理されていた。この事件に目をつけたのはシーズン2でも出てきたFBI特別捜査官フランク・ランディ。FBIを引退してまで殺人鬼「トリニティ」を追っている。マイアミでも最初の殺人バスタブでの若い女性の全裸死体が出てランディは再びマイアミに戻ってきた。シーズン2では尊敬と実の父から受けられなかった包容力、そして愛情を感じてデボラは父親のような年齢のランディと恋人同士になる。が、FBI特別捜査官であるがゆえ殺人鬼が現れるとアメリカ各地に飛ぶことになる。マイアミの警察官であるデボラにはついていくことは出来なかった。(シーズン2の殺人犯ライラの放火事件が重なったせいでもありますが)
・・・デボラは相変わらずです。正義感は強く、強気な態度なのに傷つきやすい・・・やっぱりメンドクセェ~という感じは否めません。相変わらずの男好きだし。デボラにとってランディは理想の父親の影(実際父親ほどの年齢)捜査官としての尊敬(切れ者のFBI捜査官)があり特別な存在なのはわかりますが、今回も男をとっかえひっかえ感はぬぐえませんしねえ;でもこのデボラの性格も物語の鍵だと思います。このドラマを見ているとアメリカの生活って・・・と感じる所があります。デクスターの恋人リタが妊娠する。デクスターはそれを機会にプロポーズするのですがリタはいったん拒む。「恋人と父親(夫婦)になることは意味が違うのよ」言ってみればその通りなんですがそれを言うなら、恋人が好きだからとSEXして妊娠して母親になってしまうリタの方もなんかその・・・とちょっと思ったり。まあ、リタはすでに二人の子持ちですしドラマではデクスターのプロポーズのやり方も悪かったという(感情がよくわからないという設定だから仕方ないのですが)そういう理由もあります。今回のシーズン4では「デクスター父さん奮闘記」という面も大。見ていてなんとなく 昔ウッチャンナンチャンの番組で見たアメリカンジョークを思い出しました。ちょっとうろおぼえですけどこんな感じだったかと
「世界で一番幸せな男は アメリカの家、イギリスの給料、中国の食事、妻は日本人」
しかし、順番を間違うと世界で一番不幸な男になる。
「世界で一番不幸な男とは 日本の家、中国の給料、イギリスの食事、妻はアメリカ人」
それはアメリカに限らないことなのでしょうがでもアメリカでの父親って大変だなあと感じました。。。ちょっとネタバレになりますがあの衝撃のラストを見たら次のシーズンも製作されることを願います。(というかアメリカではもう放映されてるらしいですけど)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次のシーズン5が待ち遠しいかぎりです。以上、あくまで私の個人的な感想に過ぎません。。。
「デクスター」シリーズはかなりお気に入りです。
お気に入りの海外ドラマ、シーズン4が出ていたことに気づきませんでした。以前書きましたがマイアミ警察の「血痕専門鑑識官」のデクスターが実は連続殺人犯というドラマです。テーマは「家族愛」アメリカのドラマでは基本ですね。(というよりアメリカのドラマはほぼ家族愛がテーマ)殺人鬼デクスターは心を失っているが恋人リタとその家族と付き合うことで、そして結婚し本当の家族となり良き父親を演じることで心を取り返し始める?という物語になるのでしょうか。
ーーーー以下以前のシリーズ含めネタばれがありますーーーー
シリアルキラー(連続殺人犯)の多くは幼少期に虐待を受けていることが多く人格障害の原因でもあるとも言います。ロバート・K・レスラー「FBI心理捜査官」の内容のうろ覚えなので間違ってたらすみません(汗)この本は実際にFBI心理捜査官だった作者の実録なだけに迫力がありました。当時話題になったので読んだ方も多いかと思います。
ちょっと話が変わりますが、本来なら愛されるべき親から虐待を受けると「虐待を受けているのは自分ではない、別の人物なのだ」と別人格を作ってしまうことがある。これがいわゆる多重人格(解離性同一性障害)漫画やドラマだと二重人格が多いですが人格が二人だけという事は稀で多数の人格がある場合がほとんどらしい(漫画で多数の人格を表現するのは難しそうですしね)これは当時ベストセラーになったダニエル・キイスの「24人のビリー・ミリガン」からです。実在の多重人格者の記録になるのでしょうか。ちょうど「FBI心理捜査官」が流行ってたころで続けて読んだ気がします。その流れでロバート・D・ヘラーの「診断名サイコパス」も読みました。あのころは自分の中で異常心理学?がマイブーム(死後)で「平気でうそをつく人たちー虚偽と邪悪の心理学」古本で福島章「犯罪心理学」も読みました。まあ、ほぼ内容を忘れてしまってますけど・・・・(笑)「平気でうそをつく人たち」はベストセラーになっていたので読んだ方も多いと思います。平易な訳文で読みやすかった分 内容はけっこう考えさせられました。 こういった心理学書系を読むと他人を心理学的にあてはめてしまうことがあります。しかしこれらの本でも書かれていましたが、一知半解の知識で人を判断しようとすることは危険な事だと注意をうながしていました。ちょうど家庭の医学を読んだ時と同じでしょうか。家庭の医学を読むと過敏になり、ちょっとしたことが病気の原因になっているようで怖くなったりしますから。通ってた学校の表現関係の先生に言わせると「心理学は苦手」だそうで。理由は「心に方程式をあてはめるようだから」とのこと。たしかにそういう考え方もあるのかもしれないなあと思いました。仮にみんなフロイト流に判断したらエロエロな世界になりそうですしね(完全に素人考えなんですけど)
このデクスターも通説通り?幼少期のトラウマを抱えています。
元薬中毒で密告屋の母親がチェーンソーで切り殺される所を目撃、三日間その血の海に実の兄とともに閉じ込められていたという。(デクスター自身はそのおぞましい記憶を封印して忘れてしまっている)そんなデクスターを発見し、養子に向かえ、さらに理解し導いたのは優秀な警察官であった義父のハリー・モーガンだった。危険な性質になってしまったデクスターに「闇の衝動(殺しの衝動)」の処理の仕方?を仕込んだ。「殺しの衝動が起こったら、殺されてもいい人間を殺せ。」つまり殺人鬼デクスターの標的は「殺人犯」。主に法を逃れて社会に隠れている殺人犯が標的となる。厳しい掟が決められていて標的が本当に殺人犯であるとわかったときでないと殺すことはできない。ある種正義の殺人鬼それがデクスター。デクスターは義父ハリーの教えに従い鑑識官になったが、ハリーの本当の娘(デクスターの義理の妹)デボラも父と同じ道に進み刑事になる。この奔放で下品な?義妹デボラへの愛情(といっても家族としての愛)も物語の鍵。
トラウマのため忘れていたデクスターの実の兄も その後別の施設で生活を送り成長してから 連続殺人犯「冷凍者キラー」として彼の前に現れる。これがシーズン1でした。デクスターは泣く泣く殺人鬼となった兄を殺す。シーズン2ではデクスターの過去の犠牲者の遺体が発見され「殺人鬼ベイハーバー・ブッチャー」事件となってしまう。そこへ放火魔のライラという女性もからんで事件になる。シーズン3では名前つきの殺人鬼はいませんが今回のシーズン4では「トリニティ」という殺人鬼が現れます。
アメリカ各地で連続した殺人事件が起こる。最初はバスタブで若い女性の全裸死体。次に中年女性の墜落死体。最後は中年男性の撲殺死体。必ずこの順番で3死体が出るがFBIでは自殺や通り魔として処理されていた。この事件に目をつけたのはシーズン2でも出てきたFBI特別捜査官フランク・ランディ。FBIを引退してまで殺人鬼「トリニティ」を追っている。マイアミでも最初の殺人バスタブでの若い女性の全裸死体が出てランディは再びマイアミに戻ってきた。シーズン2では尊敬と実の父から受けられなかった包容力、そして愛情を感じてデボラは父親のような年齢のランディと恋人同士になる。が、FBI特別捜査官であるがゆえ殺人鬼が現れるとアメリカ各地に飛ぶことになる。マイアミの警察官であるデボラにはついていくことは出来なかった。(シーズン2の殺人犯ライラの放火事件が重なったせいでもありますが)
・・・デボラは相変わらずです。正義感は強く、強気な態度なのに傷つきやすい・・・やっぱりメンドクセェ~という感じは否めません。相変わらずの男好きだし。デボラにとってランディは理想の父親の影(実際父親ほどの年齢)捜査官としての尊敬(切れ者のFBI捜査官)があり特別な存在なのはわかりますが、今回も男をとっかえひっかえ感はぬぐえませんしねえ;でもこのデボラの性格も物語の鍵だと思います。このドラマを見ているとアメリカの生活って・・・と感じる所があります。デクスターの恋人リタが妊娠する。デクスターはそれを機会にプロポーズするのですがリタはいったん拒む。「恋人と父親(夫婦)になることは意味が違うのよ」言ってみればその通りなんですがそれを言うなら、恋人が好きだからとSEXして妊娠して母親になってしまうリタの方もなんかその・・・とちょっと思ったり。まあ、リタはすでに二人の子持ちですしドラマではデクスターのプロポーズのやり方も悪かったという(感情がよくわからないという設定だから仕方ないのですが)そういう理由もあります。今回のシーズン4では「デクスター父さん奮闘記」という面も大。見ていてなんとなく 昔ウッチャンナンチャンの番組で見たアメリカンジョークを思い出しました。ちょっとうろおぼえですけどこんな感じだったかと
「世界で一番幸せな男は アメリカの家、イギリスの給料、中国の食事、妻は日本人」
しかし、順番を間違うと世界で一番不幸な男になる。
「世界で一番不幸な男とは 日本の家、中国の給料、イギリスの食事、妻はアメリカ人」
それはアメリカに限らないことなのでしょうがでもアメリカでの父親って大変だなあと感じました。。。ちょっとネタバレになりますがあの衝撃のラストを見たら次のシーズンも製作されることを願います。(というかアメリカではもう放映されてるらしいですけど)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次のシーズン5が待ち遠しいかぎりです。以上、あくまで私の個人的な感想に過ぎません。。。
「デクスター」シリーズはかなりお気に入りです。
ガンダムを観ました。
機動戦士ガンダムMSイグルーを観ました。
舞台はジオン軍。第603試作兵器実験部隊の特務艦「ヨーツンヘルム」乗艦のオリバー・マイ技術中尉の目を通して語られる実験兵器とそのテストパイロット達の物語。私の年齢のオッサンの多くにとって ガンダムはやっぱり影響大きい作品だと思います、特に初代「ファーストガンダム」は。シミュレーションゲームも「ギレンの野望シリーズ」という結構面白いのが出てますし。
ーーー(内容に触れています。ネタバレあり)ーーー
全編3Dアニメーションで雰囲気もリアルな感じ。キャラも実写並みの造詣ですが3D特有のクセがあり、個人的に慣れるまでちょっと時間がかかりました。(顔はリアルなのに服が、特にシワの表現は難しいのかノッペリしていて違和感が。ノーマルスーツ(宇宙服)ならあれでいいんだと思いますが)演技?も最初ちょっと大仰に感じてしまいましたが、でも今はちょっとお気に入りに。まるで小林源文さんの作品のような(笑) 個人的には久しぶりに読んだ、という感じです。
この作品のジオン軍はむちゃむちゃ「ドイツ軍」しています。ジオンの制服って本々ドイツ軍っぽいですけどこの作品ではさらに。鉄十字章みたいなのもつけてるし、袖の腕章なんかもありまさに見まごうばかり。一番「ドイツ軍してる」と思ったのは五、六話目に登場するカスペン大佐です。この人は唯一テストパイロットではありません。後半の物語でア・バオア・クー決戦の為、実験部隊である603部隊も戦闘部隊に組み込まれることになり、それが「カスペン戦闘大隊」でその指揮官がカスペン大佐。
このカスペン大佐が愛機のゲルググから降りるところなんてまんまドイツ軍の将校かと思いました。モビルスーツに乗っていたのにロングコート着てるし。。。直後補充兵が送られてくるのですがしかし皆、学徒の志願兵。少年兵を前に失望するカスペン大佐に一人、少年兵が前に出て公国への忠誠心を語るシーン。このあとみんなで「パンツァー・リート」歌い出しても違和感無いです。(映画「バルジ大作戦」ですか!!)途中で入る両軍のプロパガンダ用のニュース・フィルム?も第二次世界大戦っぽい感じがバリバリ。ミノフスキー粒子の影響もあり電波放送が古臭い感じになるのですかねえ?
このカスペン大佐の大隊に配備されるのは急造の決戦兵器モビル・ポット「オッゴ」。
劇中でも「敵はモビルスーツをジャカジャカ造ってるのにこっちはモビル・ポットに先祖がえりか」と言われてしまった兵器なのですが意外と高性能。 PS2に「ギレンの野望 アクシズの脅威」というシミュレーションゲームがあります。このゲームは結構良くできていてゲーム中でも「オッゴ」が開発できました。が、よく知らなかった私はこんなの量産するくらいならリックドム造ったほうがいいと即廃棄、物資回収という憂き目に。。。作品みるとほんとに高性能っぽいのでゲームでも使えたのかなあ。オッゴの親玉(母機?)の「ビグ・ラング」という試作兵器も出てきますが、こっちはゲームでは微妙だった気がします。
話が前後してしまいますが、個人的に二話目の戦車というか自走砲モビルスーツ?の話が好きです。
モビルタンク「ヒルドルブ」 見た目は巨大な自走砲ですが変形し、変形するとザクタンクの強力版といった形に。ジオン版ガンタンクといった所でしょうか??このヒルドルブのテスト・パイロットが元戦車教導団教官だったソンネン少佐。このキャラクターが個人的に好みです。「勘であわせろってか。・・・フン、俺の勘でねぇ」「来たな。戦争を教えてやる」かっこいいですねえ(笑
戦車兵からモビルスーツ・パイロットに転換し損ねて腐っているという人物なのですが、あんまりそんな感じがしないんです。その一端はこのヒルドルブが強いからでしょうか。ゲームにもこのヒルドルブが出てくるのですが「でかい戦車なんて使えないよな」という思い込みから一度も戦闘させませんでした。アラビアの砂漠に置きっぱなしに。。。ということはゲーム内でも変形したのかな?全然試さないまま終わってました。
三話目に「ザクⅠ」とジオン軍制式モビルスーツの座を競って負けた「ズダ」というモビルスーツも出てます。
「ズダ・・・その名前はどうよ?」ってちょっと思ってしまいましたが、ゲームではこれまた結構高性能。何といっても足が長く「占領用」ユニットとして重宝しました。ゲームでなら明らかにザクⅠより優れているように思いますが、ただし宇宙専用機です。汎用性はザクのほうが上ですね。物語では「ジオニック社のザク」「ツゥイーマット社のズダ」両社の争いがあり「ツゥイーマット社のズダ」は政治的に負けたと言うのですが(エンジンが暴走するけどね)これはドイツ軍でいう「メッサーシュミット」と「ハインケル」の争いからヒントを得たのかなあ?と思ったり。以前ドイツ空軍はハインケル社を冷遇した、というような記事を読んだことがありますし。でも最近読んだ記事だとハインケル社を冷遇していたということはないとも書かれています。(爆撃機はハインケル社製が結構あるそうです)
このズダをプロパガンダに利用し新兵器として喧伝するのですが、ふつーに「新兵器ドム」じゃだめだったのかなあ?(オデッサ作戦以後の話なのでガンダムに負けてることがもう知られてるからかな??)
この回の話は個人的に切なく悲しい。オデッサで敗退したジオン兵が宇宙に脱出ポットで逃れてくるのですがそこへ連邦軍の部隊が。手も足も出せず撃破される脱出ポット。抵抗しようとザクを出すも「地上用」のJ型なので宇宙では満足に動けずボールの餌食になっていく(これを劇中では「溺れる」と表現しています)負けた側の物語ですので総じて切なく悲しい物語なのですが。。。
第四話では宇宙戦用ズゴック「ゼーゴック」という試作兵器が登場します。
もう海洋戦を行わなくなったズゴックを宇宙用に急改造した機体で強力な武器部分は使用後に廃棄するというシステム。「いよいよ急造品ですな。ああ・・・使い捨てですか」とさみしそうに言われてしまう機体ですが、でもゲームではちょっと反則的?な兵器でした。イメージとしては「ビーム防御のないビグザム」 ビグザムほどHPは無いですが強力な「砲撃」ビームはまさにクアントビーム?並みです。でもこれって劇中では大気圏離脱してくる敵艦を攻撃するためだけの本当に局地的な兵器なんですよね。操縦も難関で主人公オリバー技術中尉も「戦いが宇宙(そら)に移った現在、必要なのか」という疑問から使用中止を具申しようとします。しかしゲームでは宇宙戦全般で使用できる強力なユニットなんですけどね。
ーーーここからは大ネタバレになりますがーーー
一年戦争の最終戦、ア・バオア・クー戦。第603試作兵器実験部隊(正確にはカスペン戦闘大隊でしょうか)は すべてのモビルスーツ、モビルポットを出撃させて友軍の退路をつくる戦闘をします。主人公オリバー技術中尉の「我々の最後の戦い、記録願います」この通信を最後に連邦軍の大軍に向かい、次々と撃墜されていくジオン機の姿。オリバー中尉の乗機「ビグ・ラング」も撃墜され、爆発。ここで映像が途切れる。そして最後の撤退する友軍艦が通る・・・個人的にはここでおわっても良かったかなあとも思いました。作品でのラストはオリバー中尉たちは生き残り帰ってきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
この作品のヒロインは第603試作兵器実験部隊に赴任してくるモニカ・キャデラック特務大尉(特務は2階級上になり中佐扱い)・・・って親衛隊とはまたちがうのかな?でもこのヒロインも結構好きです。やっぱりツンデレですよね。。。
・・・と、ガンダムを久しぶりに観ました。ガンダムは出てきませんでしたけど(記録映像でチラッと)
PS2のゲームも久しぶりにやってみようかな。
ZZ以降観ていないのでレンタルしようかと思いますが、以降は長いですねえ。
舞台はジオン軍。第603試作兵器実験部隊の特務艦「ヨーツンヘルム」乗艦のオリバー・マイ技術中尉の目を通して語られる実験兵器とそのテストパイロット達の物語。私の年齢のオッサンの多くにとって ガンダムはやっぱり影響大きい作品だと思います、特に初代「ファーストガンダム」は。シミュレーションゲームも「ギレンの野望シリーズ」という結構面白いのが出てますし。
ーーー(内容に触れています。ネタバレあり)ーーー
全編3Dアニメーションで雰囲気もリアルな感じ。キャラも実写並みの造詣ですが3D特有のクセがあり、個人的に慣れるまでちょっと時間がかかりました。(顔はリアルなのに服が、特にシワの表現は難しいのかノッペリしていて違和感が。ノーマルスーツ(宇宙服)ならあれでいいんだと思いますが)演技?も最初ちょっと大仰に感じてしまいましたが、でも今はちょっとお気に入りに。まるで小林源文さんの作品のような(笑) 個人的には久しぶりに読んだ、という感じです。
この作品のジオン軍はむちゃむちゃ「ドイツ軍」しています。ジオンの制服って本々ドイツ軍っぽいですけどこの作品ではさらに。鉄十字章みたいなのもつけてるし、袖の腕章なんかもありまさに見まごうばかり。一番「ドイツ軍してる」と思ったのは五、六話目に登場するカスペン大佐です。この人は唯一テストパイロットではありません。後半の物語でア・バオア・クー決戦の為、実験部隊である603部隊も戦闘部隊に組み込まれることになり、それが「カスペン戦闘大隊」でその指揮官がカスペン大佐。
このカスペン大佐が愛機のゲルググから降りるところなんてまんまドイツ軍の将校かと思いました。モビルスーツに乗っていたのにロングコート着てるし。。。直後補充兵が送られてくるのですがしかし皆、学徒の志願兵。少年兵を前に失望するカスペン大佐に一人、少年兵が前に出て公国への忠誠心を語るシーン。このあとみんなで「パンツァー・リート」歌い出しても違和感無いです。(映画「バルジ大作戦」ですか!!)途中で入る両軍のプロパガンダ用のニュース・フィルム?も第二次世界大戦っぽい感じがバリバリ。ミノフスキー粒子の影響もあり電波放送が古臭い感じになるのですかねえ?
このカスペン大佐の大隊に配備されるのは急造の決戦兵器モビル・ポット「オッゴ」。
劇中でも「敵はモビルスーツをジャカジャカ造ってるのにこっちはモビル・ポットに先祖がえりか」と言われてしまった兵器なのですが意外と高性能。 PS2に「ギレンの野望 アクシズの脅威」というシミュレーションゲームがあります。このゲームは結構良くできていてゲーム中でも「オッゴ」が開発できました。が、よく知らなかった私はこんなの量産するくらいならリックドム造ったほうがいいと即廃棄、物資回収という憂き目に。。。作品みるとほんとに高性能っぽいのでゲームでも使えたのかなあ。オッゴの親玉(母機?)の「ビグ・ラング」という試作兵器も出てきますが、こっちはゲームでは微妙だった気がします。
話が前後してしまいますが、個人的に二話目の戦車というか自走砲モビルスーツ?の話が好きです。
モビルタンク「ヒルドルブ」 見た目は巨大な自走砲ですが変形し、変形するとザクタンクの強力版といった形に。ジオン版ガンタンクといった所でしょうか??このヒルドルブのテスト・パイロットが元戦車教導団教官だったソンネン少佐。このキャラクターが個人的に好みです。「勘であわせろってか。・・・フン、俺の勘でねぇ」「来たな。戦争を教えてやる」かっこいいですねえ(笑
戦車兵からモビルスーツ・パイロットに転換し損ねて腐っているという人物なのですが、あんまりそんな感じがしないんです。その一端はこのヒルドルブが強いからでしょうか。ゲームにもこのヒルドルブが出てくるのですが「でかい戦車なんて使えないよな」という思い込みから一度も戦闘させませんでした。アラビアの砂漠に置きっぱなしに。。。ということはゲーム内でも変形したのかな?全然試さないまま終わってました。
三話目に「ザクⅠ」とジオン軍制式モビルスーツの座を競って負けた「ズダ」というモビルスーツも出てます。
「ズダ・・・その名前はどうよ?」ってちょっと思ってしまいましたが、ゲームではこれまた結構高性能。何といっても足が長く「占領用」ユニットとして重宝しました。ゲームでなら明らかにザクⅠより優れているように思いますが、ただし宇宙専用機です。汎用性はザクのほうが上ですね。物語では「ジオニック社のザク」「ツゥイーマット社のズダ」両社の争いがあり「ツゥイーマット社のズダ」は政治的に負けたと言うのですが(エンジンが暴走するけどね)これはドイツ軍でいう「メッサーシュミット」と「ハインケル」の争いからヒントを得たのかなあ?と思ったり。以前ドイツ空軍はハインケル社を冷遇した、というような記事を読んだことがありますし。でも最近読んだ記事だとハインケル社を冷遇していたということはないとも書かれています。(爆撃機はハインケル社製が結構あるそうです)
このズダをプロパガンダに利用し新兵器として喧伝するのですが、ふつーに「新兵器ドム」じゃだめだったのかなあ?(オデッサ作戦以後の話なのでガンダムに負けてることがもう知られてるからかな??)
この回の話は個人的に切なく悲しい。オデッサで敗退したジオン兵が宇宙に脱出ポットで逃れてくるのですがそこへ連邦軍の部隊が。手も足も出せず撃破される脱出ポット。抵抗しようとザクを出すも「地上用」のJ型なので宇宙では満足に動けずボールの餌食になっていく(これを劇中では「溺れる」と表現しています)負けた側の物語ですので総じて切なく悲しい物語なのですが。。。
第四話では宇宙戦用ズゴック「ゼーゴック」という試作兵器が登場します。
もう海洋戦を行わなくなったズゴックを宇宙用に急改造した機体で強力な武器部分は使用後に廃棄するというシステム。「いよいよ急造品ですな。ああ・・・使い捨てですか」とさみしそうに言われてしまう機体ですが、でもゲームではちょっと反則的?な兵器でした。イメージとしては「ビーム防御のないビグザム」 ビグザムほどHPは無いですが強力な「砲撃」ビームはまさにクアントビーム?並みです。でもこれって劇中では大気圏離脱してくる敵艦を攻撃するためだけの本当に局地的な兵器なんですよね。操縦も難関で主人公オリバー技術中尉も「戦いが宇宙(そら)に移った現在、必要なのか」という疑問から使用中止を具申しようとします。しかしゲームでは宇宙戦全般で使用できる強力なユニットなんですけどね。
ーーーここからは大ネタバレになりますがーーー
一年戦争の最終戦、ア・バオア・クー戦。第603試作兵器実験部隊(正確にはカスペン戦闘大隊でしょうか)は すべてのモビルスーツ、モビルポットを出撃させて友軍の退路をつくる戦闘をします。主人公オリバー技術中尉の「我々の最後の戦い、記録願います」この通信を最後に連邦軍の大軍に向かい、次々と撃墜されていくジオン機の姿。オリバー中尉の乗機「ビグ・ラング」も撃墜され、爆発。ここで映像が途切れる。そして最後の撤退する友軍艦が通る・・・個人的にはここでおわっても良かったかなあとも思いました。作品でのラストはオリバー中尉たちは生き残り帰ってきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
この作品のヒロインは第603試作兵器実験部隊に赴任してくるモニカ・キャデラック特務大尉(特務は2階級上になり中佐扱い)・・・って親衛隊とはまたちがうのかな?でもこのヒロインも結構好きです。やっぱりツンデレですよね。。。
・・・と、ガンダムを久しぶりに観ました。ガンダムは出てきませんでしたけど(記録映像でチラッと)
PS2のゲームも久しぶりにやってみようかな。
ZZ以降観ていないのでレンタルしようかと思いますが、以降は長いですねえ。