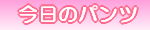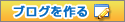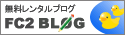十干十二支 古語の授業を思い出しました。
十干十二支 これ、古典の授業で覚えさせられました、特に十干。まさに丸暗記。
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 読み方は こう おつ へい てい ぼ き こう しん じん き
古典の授業の前、必ず小テストがありこれが99%出題されましたが当時まったく覚えられませんでした。だって意味わかんないんだもん。対して十二支の方は意味があり普通に使っている?ことなのですんなり覚えられました。子丑寅卯辰巳(ねうしとらうたつみ)までは簡単に覚えられますがこの後が正に鬼門(笑)に入ります。午(うま)まではいけるかな。そしてまさに表鬼門の未申(ひつじさる)西を表す酉(とり)、北西になる戌亥(いぬい)。
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 ねうしとらうたつみうまひつじさるとりいぬい
しかし十干はサッパリ。意味を知ったのは高校出て陰陽師が流行ったころでした。これは陰陽五行説なのです。
西洋は4大元素 火水風土 ですけど 東洋は5大元素 木火土金水なのです。これに陰(弟)と陽(兄)の二つの太極がありこれを5大元素に当てはめたものが十干です。つまり
甲(きのえ=木の兄)
乙(きのと=木の弟)
丙 (ひのえ=火の兄)
丁 (ひのと=火の弟)……以下同文。
これがわかっていれば当時面白がって覚えたと思う(苦笑)自分の高校の古典の先生は二浪して早稲田に入り学生時代、予備校で先生をしてたとか。だからか「古典は暗記」が持論でした。有無を言わさず覚えろ、と。多分受験には正しい姿勢なのでしょうが興味は薄れますよねえ。。。まあ「興味」は大学入ってそこで持て、と言う事でしょうねえ。
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 読み方は こう おつ へい てい ぼ き こう しん じん き
古典の授業の前、必ず小テストがありこれが99%出題されましたが当時まったく覚えられませんでした。だって意味わかんないんだもん。対して十二支の方は意味があり普通に使っている?ことなのですんなり覚えられました。子丑寅卯辰巳(ねうしとらうたつみ)までは簡単に覚えられますがこの後が正に鬼門(笑)に入ります。午(うま)まではいけるかな。そしてまさに表鬼門の未申(ひつじさる)西を表す酉(とり)、北西になる戌亥(いぬい)。
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 ねうしとらうたつみうまひつじさるとりいぬい
しかし十干はサッパリ。意味を知ったのは高校出て陰陽師が流行ったころでした。これは陰陽五行説なのです。
西洋は4大元素 火水風土 ですけど 東洋は5大元素 木火土金水なのです。これに陰(弟)と陽(兄)の二つの太極がありこれを5大元素に当てはめたものが十干です。つまり
甲(きのえ=木の兄)
乙(きのと=木の弟)
丙 (ひのえ=火の兄)
丁 (ひのと=火の弟)……以下同文。
これがわかっていれば当時面白がって覚えたと思う(苦笑)自分の高校の古典の先生は二浪して早稲田に入り学生時代、予備校で先生をしてたとか。だからか「古典は暗記」が持論でした。有無を言わさず覚えろ、と。多分受験には正しい姿勢なのでしょうが興味は薄れますよねえ。。。まあ「興味」は大学入ってそこで持て、と言う事でしょうねえ。
新年あけましておめでとうございます!!
新年あけましておめでとうございます。
今年は戌(犬)年。戌とは本来「滅ぶ」もしくは「切る」という意味。これは種子を残し未来を託して滅ぶ植物の一生のうちの一コマを表したものです。「滅ぶ」というと不幸な感じを受けますが「新」を産むには一度「滅」が必要なものなのです。つまりは次のステップの為の一段階。そういう年にしたいと思います。
今年は戌(犬)年。戌とは本来「滅ぶ」もしくは「切る」という意味。これは種子を残し未来を託して滅ぶ植物の一生のうちの一コマを表したものです。「滅ぶ」というと不幸な感じを受けますが「新」を産むには一度「滅」が必要なものなのです。つまりは次のステップの為の一段階。そういう年にしたいと思います。
財布を落としました(悲悲)
財布を落としました。
プリンターのインクが乏しくなり取り合えず買おうと近くのケーズ電気に行く途中、財布を落としてしまいました。ケーズ電気について気づき3往復して探しましたが見つからず交番へ。近くの交番では丁寧に調書をつくってくれて隣の交番にも聞いてくれました。するとそこに届いていると。さっそく隣の交番へ。そこでは鬼軍曹みたいな古参のお巡りさんほか数名。なんとな~く落とした私が攻められてる感じに。。。まあ、出てきたしと思っていると中身が一万三千円抜かれてました。
外国人が「財布を落としても戻ってくる日本」と評していましたが中身抜かれちゃ…。一応「遺失物横領」になるんじゃないのかなあと思いましたが言い出してこないしそういうもんか、と思いつつ交番を後に…。
年末に一万三千円は(>_<)インクも買わずに悄然と帰りました。ほんと、つらい~。
ps 今回わかったことは警察官って管轄が違うとわずか1kmない距離でも全然わからないという事。二番目の交番は市が違うのですが私の自宅からは500mほど。なのに全く地理がわからない様子には少々驚きました。
プリンターのインクが乏しくなり取り合えず買おうと近くのケーズ電気に行く途中、財布を落としてしまいました。ケーズ電気について気づき3往復して探しましたが見つからず交番へ。近くの交番では丁寧に調書をつくってくれて隣の交番にも聞いてくれました。するとそこに届いていると。さっそく隣の交番へ。そこでは鬼軍曹みたいな古参のお巡りさんほか数名。なんとな~く落とした私が攻められてる感じに。。。まあ、出てきたしと思っていると中身が一万三千円抜かれてました。
外国人が「財布を落としても戻ってくる日本」と評していましたが中身抜かれちゃ…。一応「遺失物横領」になるんじゃないのかなあと思いましたが言い出してこないしそういうもんか、と思いつつ交番を後に…。
年末に一万三千円は(>_<)インクも買わずに悄然と帰りました。ほんと、つらい~。
ps 今回わかったことは警察官って管轄が違うとわずか1kmない距離でも全然わからないという事。二番目の交番は市が違うのですが私の自宅からは500mほど。なのに全く地理がわからない様子には少々驚きました。
不思議なことに…近代の美術史って事が 2
途中だったので一応、切りのよいところに。
先日動画を見ていたら有名な美術評論家500人に「現代美術に最も影響を与えた作品は何か」というアンケートしたところピカソの「アビニョンの娘たち」だったそうです。う~ん、わかるけど…どう考えてもデュシャンじゃないかしら?
これが命題でした。自分はデュシャン、そうだなあ「泉(正式には噴水)」にしよう。少なくとも二つの意味でデュシャンが現代美術の最も大きな影響者だと思う。一つは歴史的なもの。前回書いたが1907年作である「「アビニョンの娘たち」だが発表は「ゲルニカ」の前年か同年の1936~37年だから。(「泉」は1917年アンデパンダン展)もう一つは後世への影響。確かにキュビズムは絵画の視点を変えたがデュシャンには「その後がない」と言われます。どういうことかというと現代の表現のほとんどをダダイムズ時代のデュシャンがやっているから。現代ムーブメントとして「ハプニング」「イベント」「ランドワーク」「パフォーマンス」etcと芸術ムーブがあったがどれも「どっかで見たなあ」感がいなめない。そう、それがダダイムズ、そしてデュシャンがやった表現なわけです。
というわけで自分はデュシャン押し。ま~、好きだからですけどね。「1、落ちる水 2、照明用ガス灯が与えられたとせよ」((笑))
先日動画を見ていたら有名な美術評論家500人に「現代美術に最も影響を与えた作品は何か」というアンケートしたところピカソの「アビニョンの娘たち」だったそうです。う~ん、わかるけど…どう考えてもデュシャンじゃないかしら?
これが命題でした。自分はデュシャン、そうだなあ「泉(正式には噴水)」にしよう。少なくとも二つの意味でデュシャンが現代美術の最も大きな影響者だと思う。一つは歴史的なもの。前回書いたが1907年作である「「アビニョンの娘たち」だが発表は「ゲルニカ」の前年か同年の1936~37年だから。(「泉」は1917年アンデパンダン展)もう一つは後世への影響。確かにキュビズムは絵画の視点を変えたがデュシャンには「その後がない」と言われます。どういうことかというと現代の表現のほとんどをダダイムズ時代のデュシャンがやっているから。現代ムーブメントとして「ハプニング」「イベント」「ランドワーク」「パフォーマンス」etcと芸術ムーブがあったがどれも「どっかで見たなあ」感がいなめない。そう、それがダダイムズ、そしてデュシャンがやった表現なわけです。
というわけで自分はデュシャン押し。ま~、好きだからですけどね。「1、落ちる水 2、照明用ガス灯が与えられたとせよ」((笑))
不思議なことに…近代の美術史って事が
今回の風邪はどうやら自律神経の狂いから来ているらしい、との事。確かに呼吸すると「ヒーヒー」言うのに炎症は無く、また自律神経系とは違い鼻水がひどいんです。特に後ろに漏れて痰になるのがつらい。咳をしすぎて横っ腹が痛くて痛くて…。「もう咳はいやだ」との思いから病院から出された咳止めシロップの回数を守らず既に全部飲んでしまいました。しかも飲み薬の咳止めももうない…。両方とも構成がカフェインと似ているので寝る前にはあまり使わないでくださいと薬剤師さんから言われてたのですが…おかげで今日も全然眠れない。だけど飲み薬の方は「夕食後に飲む」となっていてなんか矛盾するような。
先日動画を見ていたら有名な美術評論家500人に「現代美術に最も影響を与えた作品は何か」というアンケートしたところピカソの「アビニョンの娘たち」だったそうです。う~ん、わかるけど…どう考えてもデュシャンじゃないかしら?
「アビニョンの娘たち」は一番最初のキュビズムの絵画だと言われています。キュビズムは直訳されて「立体派」と言われますがちょっと違う気がする。これだとニュアンスが伝わりにくい気が。立体的な「視点」で描かれた絵画と言う方がしっくりきます。これについてよく言われるのが「横顔と正面から見た顔を一緒に描いた」。専門家に言わせると分析的キュビズムというやつです。なんだかよくわからない分類はおいといて、1907年時代は後期印象派・表現主義が世を謳歌している時代。ビビットな色彩、どぎつい表現の時代っすね。漫画チックな表現でもあります。ゴッホは先駆だっただけに時代を謳歌できず不遇でしたがピカソは違います。彼は基本的に売れる絵を描きました。時代が印象派なら印象派的な絵を(ピカソは時代がちがいますから描いてないけど)表現主義の時代なら表現主義で絵を描きました。単なるミーハー?そうだったのかなあ?でも若い頃にはありがちっちゃーありがちだし、なんでもやってみたいと思うものです。しかしやっぱり「売れる」事を考えていたのは間違いないと思います。それはこの「アビニョンの娘たち」が物語っています。
「アビニョンの娘たち」が制作されたのは1907年。しかし発表されたのはたぶん1930年代。「ゲルニカ」作成開始の1936年頃だと思います。それは何故?
1907年、27歳で後期印象派、表現主義の画家として売れていたピカソのもとには画商や評論家が出入りしていた。その一人に「傑作を描き上げた。これは時代を変える。今度見せる」と言って満を持してみせたのが「アビニョンの娘たち」。その現代(1907年当時の)を超越した表現は評論家を圧倒し唸らせる…はずだった。
しかしピカソの「アビニョンの娘たち」を一目見た評論家は眉をひそめ、「こんな絵描いてもしょうがない。もっとちゃんとした絵を描け。」全く評価されませんでした。ピカソはこの絵の発表を取りやめ、また表現主義の絵を描き始めました。
評論家というものは往々にしてこういうものです。芸術とは「時代精神の現れ」と言う説がある。トルストイによれば「今に現れた神の歌」ハイデガーによると「直観」である芸術。つまり評論家というものは、優秀であれば優秀なほど「現在」しか見えないのかもしれない。経済評論家が株で大儲けしたのを聞いたこと無いように(なかにはいるかもしれないが)、芸術評論家の多くが「先の目」(先見の明)を持っていないのかもしれない。
・・・あきません。久しぶりに頭を使ってしまったら(苦笑)頭痛がしてきました。こんなお話はこれまでにします(汗、汗)ただでさえ片頭痛で悩んでるのに・・・。
先日動画を見ていたら有名な美術評論家500人に「現代美術に最も影響を与えた作品は何か」というアンケートしたところピカソの「アビニョンの娘たち」だったそうです。う~ん、わかるけど…どう考えてもデュシャンじゃないかしら?
「アビニョンの娘たち」は一番最初のキュビズムの絵画だと言われています。キュビズムは直訳されて「立体派」と言われますがちょっと違う気がする。これだとニュアンスが伝わりにくい気が。立体的な「視点」で描かれた絵画と言う方がしっくりきます。これについてよく言われるのが「横顔と正面から見た顔を一緒に描いた」。専門家に言わせると分析的キュビズムというやつです。なんだかよくわからない分類はおいといて、1907年時代は後期印象派・表現主義が世を謳歌している時代。ビビットな色彩、どぎつい表現の時代っすね。漫画チックな表現でもあります。ゴッホは先駆だっただけに時代を謳歌できず不遇でしたがピカソは違います。彼は基本的に売れる絵を描きました。時代が印象派なら印象派的な絵を(ピカソは時代がちがいますから描いてないけど)表現主義の時代なら表現主義で絵を描きました。単なるミーハー?そうだったのかなあ?でも若い頃にはありがちっちゃーありがちだし、なんでもやってみたいと思うものです。しかしやっぱり「売れる」事を考えていたのは間違いないと思います。それはこの「アビニョンの娘たち」が物語っています。
「アビニョンの娘たち」が制作されたのは1907年。しかし発表されたのはたぶん1930年代。「ゲルニカ」作成開始の1936年頃だと思います。それは何故?
1907年、27歳で後期印象派、表現主義の画家として売れていたピカソのもとには画商や評論家が出入りしていた。その一人に「傑作を描き上げた。これは時代を変える。今度見せる」と言って満を持してみせたのが「アビニョンの娘たち」。その現代(1907年当時の)を超越した表現は評論家を圧倒し唸らせる…はずだった。
しかしピカソの「アビニョンの娘たち」を一目見た評論家は眉をひそめ、「こんな絵描いてもしょうがない。もっとちゃんとした絵を描け。」全く評価されませんでした。ピカソはこの絵の発表を取りやめ、また表現主義の絵を描き始めました。
評論家というものは往々にしてこういうものです。芸術とは「時代精神の現れ」と言う説がある。トルストイによれば「今に現れた神の歌」ハイデガーによると「直観」である芸術。つまり評論家というものは、優秀であれば優秀なほど「現在」しか見えないのかもしれない。経済評論家が株で大儲けしたのを聞いたこと無いように(なかにはいるかもしれないが)、芸術評論家の多くが「先の目」(先見の明)を持っていないのかもしれない。
・・・あきません。久しぶりに頭を使ってしまったら(苦笑)頭痛がしてきました。こんなお話はこれまでにします(汗、汗)ただでさえ片頭痛で悩んでるのに・・・。