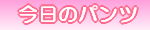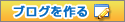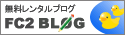人ってやっぱ、インパール…なのかなあ?汗
自律神経系をおかしくしてから何も無いのに咳が続くという症状に悩まされてきました。酷くなると息苦しくてだるくて立てなくなる。座っていてもだるいというか、苦しいというかとにかくつらい。かといって横になっても苦しくて眠れない。どこがどう苦しいのか自分でもよくわからない程なのですが明らかな症状は咳なのです。この状態になると「喘息じゃないか?」と疑うくらい咳が続く。軽い咳が夕方位から出始めるという結核を疑った事も。冬から春にかけて出る事が多くはじめのうちは花粉症かアレルギーだと思い込んでました。そして夏が最も症状が重くなる…。でも寒い時期はほとんど症状がでません。しかし今週になってから軽い咳が出始めました。「またか…汗」とうんざりし始めていたら喉が痛くなってきた。普通に風邪でした(苦笑)でもこれはこれでつらいなあ…風邪ひくのは一昨年ぶりかな?
久しぶりに梅原猛を読んでます。病院帰りに古本屋によって「黄泉の王 私見 高松塚古墳」を買いました。まだ最初ですが被葬者(葬られてる人)は弓削皇子ではないか?という内容です。弓削皇子は謎の死を遂げた人物。当時の政争に敗れたから死んだのではないか。怨霊候補ですね。だからあんな美しい壁画が描かれその世界(死の世界)に封じ込め出られないようにしたのだ…と言う事だと思います、多分。まだ最初しか読んでないけど。
哲学者(仏教学者)梅原猛は独自の歴史観で「梅原歴史学」と言われるほど。ちょうど推理作家の松本清張が「松本歴史学」と言われるのと同じですね。門外漢としてどっちも学界からは無視されてますけど(苦笑)
「梅原歴史学」と言えば「怨霊歴史学」ですね。一番有名なのは「隠された十字架 法隆寺論」です。法隆寺には7つの謎がある。その謎を解いていくと「法隆寺は聖徳太子の怨霊を封じ込めた寺である」というもの。
そして「水底の歌 柿本人麻呂論」。万葉集で天皇に挽歌を送るほどなのに正史である日本書紀にその名前が全然出てこない柿本人麻呂。天皇の死を悼む歌(挽歌)を詠むほどなのだからある程度の位が無ければおかしいのに。万葉集の歌を紐解くと「私は明日水死する」というような歌がある。つまり柿本人麻呂は政争で負けて水死刑に処せられたのではないか。だから正史から名を消されたのではないか。しかし正史には柿本佐留(さる)という謎の人物が載っている。これが実は人麻呂で罪を犯したから「人」ではなく「さる」にされたのではないか?というもの。
たまらないっすねえ(笑)自分が大好きだった小松和彦民俗学も最初はこんな感じだったのに。何べんも書きますがこの前の「京都 妖界案内」にはがっかりしました。「これは鬼門封じ」「こっちは大将軍封じ」「あれは鬼を内に閉じ込めるもの」つまり「みんな怨霊とは関係ない」だから「平安京は怨霊封じではない」結論「平安京を造った桓武天皇は怨霊を恐れてなかった」
これは小松和彦の代表作「憑霊信仰論」(つきもの筋の研究)の冒頭で「妖怪学がただの分類に終わってはならない」と言っているのに反しているように思う。こういう論法は梅原猛に言わせると「立派な解剖所見をみているようなもの」で「肝臓はここ、ここに潰瘍があると書かれているだけ」ゆえにそれをまとめても「その人物を本当に理解したわけではない」というもの。いわゆる「木を見て森を見ず」って事ですかね。木にはやたら詳しいけど森全体の視点が欠けている。
やはり京都は怨霊封じだと思います。各所見は「鬼門封じ」「代将軍封じ」「方角封じ」かもしれないけど、それらを積み上げたピラミッドの頂点、究極の目標は「怨霊を封じたいため」だと思うんです。「鬼門封じ」「代将軍封じ」「方角封じ」はそのブロックに過ぎないと思います。歴史上、桓武天皇はかなり怨霊に付きまとわれてますから。「平安」な京をつくりたくなるのもさもありなんと思うんですよね。。。
梅原猛も歴史学者の細かい視点を認めつつ、教えられつつも日本の歴史学者の全体の視点の無さを嘆いています。いわく「…私は考古学者の報告書を数多く読むようになったが、私は日本の考古学には、その方法の上において、重大な誤謬があるのではないかと思うようになった。」「考古学者はあたかも自分の学問は自然科学のように思っている」
誤謬(ごびゅう)とは間違いの事。科学者は偉くなるほどこの誤謬を認められなくなる。プライドでしょうかねえ。。。
ちなみに梅原猛は堂々と誤謬(まちがい)を認めています。それは「神々の流竄」という本。
「神々の流竄(るざん)」の内容は 元々「国津神」を信仰する民族が大和地方に住んでいた。しかし「天津神」を信仰する民族が九州から攻め上ってきて大和地方を占領し元々住んでいた「国津神」を出雲地方に追いやったのだ、というもの。というかその「国津神だけ出雲地方に島流し(流竄)にした」というものです。「天津神」を信仰する民族が後々大和朝廷=天皇家になる。でもこの本の冒頭で梅原猛は「これは誤謬(まちがい)だ」と言ってるんですよね(笑)
この本が書かれた1973年当時はまだ通用するかもしれない理論(?)だったのかもしれないが後々考古学の発見(荒神谷古墳など)があり出雲は大和以前から国家があったと証明されていきます。しかしながら自分が買ったこの古本は第4版。しかも1992年に再版されたもの。間違いと認めつつも、そこには何かしらの輝きがあるのだと思います。まさに「シャイニング」。ただ「これは間違いですよ~」と前文に書かれているものを中々情熱を持って(?)読めませんでした。が、誤謬とは言え、面白かったです。
ただ、こうやって誤謬を認められる高位者(?)は本当に数少ないと思います。翻って自分もそう。「間違った!(やべえ…)」と思いつつ押し通した経験も。今振り返れば顔が赤くなります。しかし「顔が赤くなる」では済まないような事も。それは大東亜戦争時代の「インパール作戦」に例えられます。自分はNHK取材班「責任なき戦場」という本でよく知りました。NHKというとちとビミョ~と思わなくもないですがこの本はよく書けていると思います。これはNHK特集「ドキュメント太平洋戦争」というシリーズの一巻。またまたNHK特集というとビミョ~な感じを持ちますが、これが造られた時代はちょうどバブルの真っ最中。ですので「反日」というよりバブルに狂奔する企業を批判の対象としています。一見の価値はあると思います。インパール作戦で唯一、ただ一人責任を取らされた(正確には無視された)食糧、弾薬無く一番最初に撤退を決めた佐藤高徳中将の「大本営、総軍、方面軍という馬鹿の三乗がインパールの悲劇を産んだのである」そして大本営で「牟田口がやりたい、と言っているのだからやらせてやろう」この言葉が印象に残りました。自分の間違い、責任って本当に認められないものなのだ…。
久しぶりに梅原猛を読んでます。病院帰りに古本屋によって「黄泉の王 私見 高松塚古墳」を買いました。まだ最初ですが被葬者(葬られてる人)は弓削皇子ではないか?という内容です。弓削皇子は謎の死を遂げた人物。当時の政争に敗れたから死んだのではないか。怨霊候補ですね。だからあんな美しい壁画が描かれその世界(死の世界)に封じ込め出られないようにしたのだ…と言う事だと思います、多分。まだ最初しか読んでないけど。
哲学者(仏教学者)梅原猛は独自の歴史観で「梅原歴史学」と言われるほど。ちょうど推理作家の松本清張が「松本歴史学」と言われるのと同じですね。門外漢としてどっちも学界からは無視されてますけど(苦笑)
「梅原歴史学」と言えば「怨霊歴史学」ですね。一番有名なのは「隠された十字架 法隆寺論」です。法隆寺には7つの謎がある。その謎を解いていくと「法隆寺は聖徳太子の怨霊を封じ込めた寺である」というもの。
そして「水底の歌 柿本人麻呂論」。万葉集で天皇に挽歌を送るほどなのに正史である日本書紀にその名前が全然出てこない柿本人麻呂。天皇の死を悼む歌(挽歌)を詠むほどなのだからある程度の位が無ければおかしいのに。万葉集の歌を紐解くと「私は明日水死する」というような歌がある。つまり柿本人麻呂は政争で負けて水死刑に処せられたのではないか。だから正史から名を消されたのではないか。しかし正史には柿本佐留(さる)という謎の人物が載っている。これが実は人麻呂で罪を犯したから「人」ではなく「さる」にされたのではないか?というもの。
たまらないっすねえ(笑)自分が大好きだった小松和彦民俗学も最初はこんな感じだったのに。何べんも書きますがこの前の「京都 妖界案内」にはがっかりしました。「これは鬼門封じ」「こっちは大将軍封じ」「あれは鬼を内に閉じ込めるもの」つまり「みんな怨霊とは関係ない」だから「平安京は怨霊封じではない」結論「平安京を造った桓武天皇は怨霊を恐れてなかった」
これは小松和彦の代表作「憑霊信仰論」(つきもの筋の研究)の冒頭で「妖怪学がただの分類に終わってはならない」と言っているのに反しているように思う。こういう論法は梅原猛に言わせると「立派な解剖所見をみているようなもの」で「肝臓はここ、ここに潰瘍があると書かれているだけ」ゆえにそれをまとめても「その人物を本当に理解したわけではない」というもの。いわゆる「木を見て森を見ず」って事ですかね。木にはやたら詳しいけど森全体の視点が欠けている。
やはり京都は怨霊封じだと思います。各所見は「鬼門封じ」「代将軍封じ」「方角封じ」かもしれないけど、それらを積み上げたピラミッドの頂点、究極の目標は「怨霊を封じたいため」だと思うんです。「鬼門封じ」「代将軍封じ」「方角封じ」はそのブロックに過ぎないと思います。歴史上、桓武天皇はかなり怨霊に付きまとわれてますから。「平安」な京をつくりたくなるのもさもありなんと思うんですよね。。。
梅原猛も歴史学者の細かい視点を認めつつ、教えられつつも日本の歴史学者の全体の視点の無さを嘆いています。いわく「…私は考古学者の報告書を数多く読むようになったが、私は日本の考古学には、その方法の上において、重大な誤謬があるのではないかと思うようになった。」「考古学者はあたかも自分の学問は自然科学のように思っている」
誤謬(ごびゅう)とは間違いの事。科学者は偉くなるほどこの誤謬を認められなくなる。プライドでしょうかねえ。。。
ちなみに梅原猛は堂々と誤謬(まちがい)を認めています。それは「神々の流竄」という本。
「神々の流竄(るざん)」の内容は 元々「国津神」を信仰する民族が大和地方に住んでいた。しかし「天津神」を信仰する民族が九州から攻め上ってきて大和地方を占領し元々住んでいた「国津神」を出雲地方に追いやったのだ、というもの。というかその「国津神だけ出雲地方に島流し(流竄)にした」というものです。「天津神」を信仰する民族が後々大和朝廷=天皇家になる。でもこの本の冒頭で梅原猛は「これは誤謬(まちがい)だ」と言ってるんですよね(笑)
この本が書かれた1973年当時はまだ通用するかもしれない理論(?)だったのかもしれないが後々考古学の発見(荒神谷古墳など)があり出雲は大和以前から国家があったと証明されていきます。しかしながら自分が買ったこの古本は第4版。しかも1992年に再版されたもの。間違いと認めつつも、そこには何かしらの輝きがあるのだと思います。まさに「シャイニング」。ただ「これは間違いですよ~」と前文に書かれているものを中々情熱を持って(?)読めませんでした。が、誤謬とは言え、面白かったです。
ただ、こうやって誤謬を認められる高位者(?)は本当に数少ないと思います。翻って自分もそう。「間違った!(やべえ…)」と思いつつ押し通した経験も。今振り返れば顔が赤くなります。しかし「顔が赤くなる」では済まないような事も。それは大東亜戦争時代の「インパール作戦」に例えられます。自分はNHK取材班「責任なき戦場」という本でよく知りました。NHKというとちとビミョ~と思わなくもないですがこの本はよく書けていると思います。これはNHK特集「ドキュメント太平洋戦争」というシリーズの一巻。またまたNHK特集というとビミョ~な感じを持ちますが、これが造られた時代はちょうどバブルの真っ最中。ですので「反日」というよりバブルに狂奔する企業を批判の対象としています。一見の価値はあると思います。インパール作戦で唯一、ただ一人責任を取らされた(正確には無視された)食糧、弾薬無く一番最初に撤退を決めた佐藤高徳中将の「大本営、総軍、方面軍という馬鹿の三乗がインパールの悲劇を産んだのである」そして大本営で「牟田口がやりたい、と言っているのだからやらせてやろう」この言葉が印象に残りました。自分の間違い、責任って本当に認められないものなのだ…。
観応の擾乱の前の話・・・ですねえ。
前回「観応の擾乱」という本が中公新書から出てそれについ書こうかと思いましたが、なんかまとめられなさそう(汗)…だったので断念。今回、病院から帰ってきたということで再度挑戦、ですけどなんせ南北朝が絡みますからねえ・…。まず、そこからですか…。
そもそもの発端は後嵯峨天皇。時代はまだ鎌倉時代ですが後嵯峨天皇が皇統を二つに割ってしまったのです。どういう事かと言うと嵯峨天皇は院政を行うため皇太子の後深草天皇に皇位を譲り上皇になります。が、約10年後に何故か「弟に皇位を譲れ」と命令。(上皇、法皇に権限がある)院政期なのでその命令は実行され弟は亀山天皇になりました。
なんでこんな事したんでしょう?「鎌倉幕府の画策」というのが教科書の答え。でも幕府はその後、兄弟二つに割れた「皇室」の仲を取り持ち、北条時宗は「皇位は兄、弟の家系で順番にすること」という解決案を出します。つまり
①後深草天皇(兄)ー④伏見天皇ー⑤後伏見天皇 …(持明院統)→後の北朝
後嵯峨天皇< ⑦花園天皇
②亀山天皇(弟) ―③後宇多天皇ー⑥後二条天皇 …(大覚寺統)
⑧後醍醐天皇 ーーー→後の南朝
…と、いった具合。兄の系統、弟の系統との持ち回りになってしまった皇位。各系統が院政を行った場所にちなみ兄の系統を「持明院統」、弟の系統を「大覚寺統」と言いました。また、この「皇位を両統でやり取りする事」を「両統迭立(てつりつ)」と言いました。「迭立」とは「並び立つものが順番に」という意味だそうです。
この辺はもー、わかんなかったですね。なんでこうなったんでしょう???幕府から見たら「最高権力が二つある」ということは最悪だと思うのです。例えば幕府に反対する勢力があった時、「最高権力が二つ」しかも対立してたら幕府が重きを置いていない方に駆け込んで「幕府を倒しましょう」とそそのかしたりもできる。それこそ一方から「朝敵である鎌倉幕府を討て」なんて治罰の綸旨が出されてしまう、こんな事にもなりかねない。実際、そうなって大変なことになっていくんですけど。
こんな不利なことホントに「幕府が画策」したのか???そう疑う説も少なくありません。
時代が下がって徳川家康が本願寺を西と東に別けた。「戦国最大の怪物」と言われた一向宗「一向一揆」本願寺。ゲーム「信長の野望」だと大抵一向一揆も普通の一揆に「毛が生えた」程度のものですが、本当は信長がその本拠石山本願寺を10年攻めて全く落とせなかった。しかも女子供まで住民全員が戦闘員。ベトコン顔負けです。確かに毛利の後押しもありましたが水軍戦で織田水軍が勝利してからも頑強に抵抗され、結局朝廷を動かし時の天皇から調停案を出してもらって開城させました。後々「刀狩り」して住民の牙を抜いた後も秀吉、家康ともに「本願寺奉行」というものを置いてるくらいです。家康はまだ三河の小大名時代に一向宗に手痛い目にあわされている。一向宗を挑発し鎮圧しようとしたら、有力な家臣の中からも一向一揆に参加するものが多数出たからです。家康の懐刀、本多正信はこれで三河を出奔。後にまた仕えることになります。
だから家康は宗教の恐ろしさを身をもって知っていたんでしょうねえ。一向宗は「死後は必ず極楽浄土」。この辺りはキリスト教など一神教にも似てますし。そこで家康は本願寺を東西二つに別けました。すると二派は「こっちが正統、向こうは枝葉」と主張し始め対立。つまり互いに「敵」をつくり御上に反抗しないようにしたと言われています。これはインドを支配していたイギリスが撤退する時、インド国内のイスラム教徒に「パキスタン」をつくらせそれを国家として認めた、と同じ意味ですね。パキスタンというムスリムの国ができたおかげでインドはイギリスのこれまでしてきた酷い植民地政策をあまり攻めなくなり、むしろ同族であるパキスタンと争い始めた。これがイギリス、そして家康の目的でした。
ただ確かに家康の本願寺政策は成功しましたがこれは「刀狩り」という武力を奪っていたため。インドとパキスタンの対立は激化しご存知の通り「核兵器競争」に発展、両国が核保有国になって冷戦化しました。思えば中東といい世界の大問題の半分以上はイギリスのせいじゃないのかしら?それもすべては「ひどい植民地政策」を隠すため。翻って見るとインフラ整備までした国が恨まれるという皮肉。結局「負けた国」は「国破れて山河あり」の心境になりますねえ。。。でも、これももしかしたらアメリカによる分断政策???
ちと話がずれましたが以上と同じように、幕府の目的は「朝廷に派閥をつくる事」「それを相争わせること」により「弱体を図った」…のでしょうか?この政策の中心は六波羅探題(幕府による朝廷を監視する機関)でしたがホントにそこまで考えて動いてたのかしら?
ともかく、天皇家が兄、弟の系統に分かれてしまった。そのうち「弟が天皇になれるなら私も」とばかりに系統内での弟までもが天皇になりはじめました。最初の図の最後、4人になったのはそれが原因。こうなってしまったら本来、こんなことは無いのですが天皇でいられる期間というのが決められました。それはほぼ10年。10年経ったら別系統に皇位を移さなければならない。
しかし図の中で最後の⑧後醍醐天皇。この御方も任期は10年と決められていました。しかし弟の系統でその中でも弟である後醍醐天皇は何故か「皇位は自分の系統が今後継いで行くべきだ」と考えました。とにかく一番高貴であると考えていたとしか思えません。なんでそうなのか…よくわかりませんけど、今後の行動がそう示しています。兄は早死にしましたがその息子を差し置いて「皇統は朕が子孫が継いで行く」と決断。その為にしなければならないこと、それが鎌倉幕府を倒す事でした。
…今でこそ、こういう流れがわかりましたが高校時代は無理でしたねえ(苦笑)歴史って面白いと思ったのは何度も書きますが「鬼がつくった国・日本」を読んでから。でも最近の小松先生は…個人的にはちょっと残念な感じです。どシロウトの見方に過ぎませんが「木を見て…」な感じがするんです。。。。。。
そもそもの発端は後嵯峨天皇。時代はまだ鎌倉時代ですが後嵯峨天皇が皇統を二つに割ってしまったのです。どういう事かと言うと嵯峨天皇は院政を行うため皇太子の後深草天皇に皇位を譲り上皇になります。が、約10年後に何故か「弟に皇位を譲れ」と命令。(上皇、法皇に権限がある)院政期なのでその命令は実行され弟は亀山天皇になりました。
なんでこんな事したんでしょう?「鎌倉幕府の画策」というのが教科書の答え。でも幕府はその後、兄弟二つに割れた「皇室」の仲を取り持ち、北条時宗は「皇位は兄、弟の家系で順番にすること」という解決案を出します。つまり
①後深草天皇(兄)ー④伏見天皇ー⑤後伏見天皇 …(持明院統)→後の北朝
後嵯峨天皇< ⑦花園天皇
②亀山天皇(弟) ―③後宇多天皇ー⑥後二条天皇 …(大覚寺統)
⑧後醍醐天皇 ーーー→後の南朝
…と、いった具合。兄の系統、弟の系統との持ち回りになってしまった皇位。各系統が院政を行った場所にちなみ兄の系統を「持明院統」、弟の系統を「大覚寺統」と言いました。また、この「皇位を両統でやり取りする事」を「両統迭立(てつりつ)」と言いました。「迭立」とは「並び立つものが順番に」という意味だそうです。
この辺はもー、わかんなかったですね。なんでこうなったんでしょう???幕府から見たら「最高権力が二つある」ということは最悪だと思うのです。例えば幕府に反対する勢力があった時、「最高権力が二つ」しかも対立してたら幕府が重きを置いていない方に駆け込んで「幕府を倒しましょう」とそそのかしたりもできる。それこそ一方から「朝敵である鎌倉幕府を討て」なんて治罰の綸旨が出されてしまう、こんな事にもなりかねない。実際、そうなって大変なことになっていくんですけど。
こんな不利なことホントに「幕府が画策」したのか???そう疑う説も少なくありません。
時代が下がって徳川家康が本願寺を西と東に別けた。「戦国最大の怪物」と言われた一向宗「一向一揆」本願寺。ゲーム「信長の野望」だと大抵一向一揆も普通の一揆に「毛が生えた」程度のものですが、本当は信長がその本拠石山本願寺を10年攻めて全く落とせなかった。しかも女子供まで住民全員が戦闘員。ベトコン顔負けです。確かに毛利の後押しもありましたが水軍戦で織田水軍が勝利してからも頑強に抵抗され、結局朝廷を動かし時の天皇から調停案を出してもらって開城させました。後々「刀狩り」して住民の牙を抜いた後も秀吉、家康ともに「本願寺奉行」というものを置いてるくらいです。家康はまだ三河の小大名時代に一向宗に手痛い目にあわされている。一向宗を挑発し鎮圧しようとしたら、有力な家臣の中からも一向一揆に参加するものが多数出たからです。家康の懐刀、本多正信はこれで三河を出奔。後にまた仕えることになります。
だから家康は宗教の恐ろしさを身をもって知っていたんでしょうねえ。一向宗は「死後は必ず極楽浄土」。この辺りはキリスト教など一神教にも似てますし。そこで家康は本願寺を東西二つに別けました。すると二派は「こっちが正統、向こうは枝葉」と主張し始め対立。つまり互いに「敵」をつくり御上に反抗しないようにしたと言われています。これはインドを支配していたイギリスが撤退する時、インド国内のイスラム教徒に「パキスタン」をつくらせそれを国家として認めた、と同じ意味ですね。パキスタンというムスリムの国ができたおかげでインドはイギリスのこれまでしてきた酷い植民地政策をあまり攻めなくなり、むしろ同族であるパキスタンと争い始めた。これがイギリス、そして家康の目的でした。
ただ確かに家康の本願寺政策は成功しましたがこれは「刀狩り」という武力を奪っていたため。インドとパキスタンの対立は激化しご存知の通り「核兵器競争」に発展、両国が核保有国になって冷戦化しました。思えば中東といい世界の大問題の半分以上はイギリスのせいじゃないのかしら?それもすべては「ひどい植民地政策」を隠すため。翻って見るとインフラ整備までした国が恨まれるという皮肉。結局「負けた国」は「国破れて山河あり」の心境になりますねえ。。。でも、これももしかしたらアメリカによる分断政策???
ちと話がずれましたが以上と同じように、幕府の目的は「朝廷に派閥をつくる事」「それを相争わせること」により「弱体を図った」…のでしょうか?この政策の中心は六波羅探題(幕府による朝廷を監視する機関)でしたがホントにそこまで考えて動いてたのかしら?
ともかく、天皇家が兄、弟の系統に分かれてしまった。そのうち「弟が天皇になれるなら私も」とばかりに系統内での弟までもが天皇になりはじめました。最初の図の最後、4人になったのはそれが原因。こうなってしまったら本来、こんなことは無いのですが天皇でいられる期間というのが決められました。それはほぼ10年。10年経ったら別系統に皇位を移さなければならない。
しかし図の中で最後の⑧後醍醐天皇。この御方も任期は10年と決められていました。しかし弟の系統でその中でも弟である後醍醐天皇は何故か「皇位は自分の系統が今後継いで行くべきだ」と考えました。とにかく一番高貴であると考えていたとしか思えません。なんでそうなのか…よくわかりませんけど、今後の行動がそう示しています。兄は早死にしましたがその息子を差し置いて「皇統は朕が子孫が継いで行く」と決断。その為にしなければならないこと、それが鎌倉幕府を倒す事でした。
…今でこそ、こういう流れがわかりましたが高校時代は無理でしたねえ(苦笑)歴史って面白いと思ったのは何度も書きますが「鬼がつくった国・日本」を読んでから。でも最近の小松先生は…個人的にはちょっと残念な感じです。どシロウトの見方に過ぎませんが「木を見て…」な感じがするんです。。。。。。
日本語って難しい。「乱」「変」「役」そして「擾乱」
「観応の擾乱」で思い出したんですけど日本史には争いを表す言葉が複数ありますよね。例えば応仁の乱、薬子の変、前九年の役など、「乱」「変」「役」そして観応の擾乱の「擾乱」。それぞれ違いがありますよねえ。
一番わかりやすいのは「役」でしょうか。これは対外戦争を指して使われてますよね。正確に言うと異民族との戦争かな。こっちから仕掛けた場合でも仕掛けられた場合でも異民族との戦争は「役」になってます。元寇は元(モンゴル帝国)が攻めてきたという意味で2回の戦争があり、一度目が「文永の役」二回目が「弘安の役」。モンゴル人は日本人では当然ありませんから。ちなみに平安時代に東北地方を朝廷が侵略した戦争も「前九年の役」と「後三年の役」。つまり当時の東北地方は日本ではなく、住んでいる人も異民族と考えらえていた証拠です。実際東北人は「蝦夷(えみし)」と呼ばれ異民族と考えられていました。この蝦夷(えみし)は「東に住む野蛮人=東夷」からきた言葉であろう、と言われています。そして初めて「日本」が文献に載ったは三国志時代の中国。「魏志倭人伝」は「魏書」の中の「東夷伝」の略称。当時の中国からしたら日本(ヤマタイ=ヤマト?)は「東の島に住む野蛮人=東夷」だったわけです。だから「卑弥呼」という「卑しい」字を女王にも使ってる。本来の意味は「日(の)御子」または「日(の)巫女」だったのではないかとも言われてます。
多分意味的に一番広いのが「乱」でしょうかねえ。でもこれは「反乱」の意味でしょうか。もっと古い時代、神話の時代にもあったでしょうが奈良時代の戦争はほとんどが「乱」でした。恵美押勝にしろ、藤原広嗣にしろ「乱」。どっちも反乱ですもんね。時代は下がって源平の争乱も「乱」。異なる陣営「平氏」と「源氏」の争いでしたが「乱」。これはどちらも一応は「官軍」でしたから「内乱」と見たんでしょうかねえ。ただ勝ったからいいようなものの、最初の源氏の錦の御旗は「以仁王の令旨」。「王」となっていることでわかるように皇位からはかなりかな~り遠いお方。この立場の人が「皇族だから」と「令旨」なんて乱発したらそれこそ「乱」ばっかになりそう。対して平氏にはれっきとした安徳天皇という方がおられた。その後結局、白河法皇に「無し」にされてしまいますが(院政時代ですから上皇、法皇が実権を握っている)、この時点では三種の神器もお持ちになった正式な天皇でしたもんね。
また時代が下がり時代の分かれ目たる「応仁の乱」。これは室町幕府の後継問題ですからやっぱり「内乱」と見たのでしょうか?それにしちゃあ戦争っぽい。けど当時、策謀に長けた東軍筆頭の細川勝元が西軍を「朝敵」にしようと画策、西軍に対して「治罰の綸旨」(天皇家の敵)を出してくれるよう頼みます。けど後花園上皇は「武家同志の私闘である」として綸旨は出しませんでした。つまり朝廷が公式に「武家の内乱」としたんでしょう。だからあれだけの大戦争でも「乱」なんでしょうか。
最後に「変」。これは「薬子の変」など武力を用いても限定的な「クーデター」に使われているような気がします。またまた時代が下がり「本能寺の変」。あれもクーデターですもんね。明智光秀は一万の軍勢を動かしたと言われますが、大兵力どうしのぶつかり合いはその後の秀吉との「山崎の合戦」という「合戦」になってますもんねえ。またまたちなみに明治時代、軍参謀本部で使われていた日本の合戦の解説書によると「関ケ原の合戦」は「関ケ原の役」になっているそうです。「役」ですかあ。。。う~ん、なんでだろう、いままでの説がくずれてしまいそう(汗)
と、色々おもいましたが、どの視点で見て「乱」や「変」、「役」になるのだろう?と考え直すとやっぱり「天皇家から見て」なんじゃないかなあと思い至りました。「本能寺」以降がちょっと微妙ですけど、それは鎌倉はもちろん室町もやっぱ日本の主人は「天皇家」だった証拠かもなあ…と。戦国時代という「何でもあり」になってから変わったのかもなあ…とつい浅知恵。知らないだけで「本能寺」以外の例外もいっぱいあるんでしょうねえ。しかし日本は2000年続いた長~い国なんですねえ。。。そして聞きなれない「擾乱」とは「世を乱し騒がすこと」だそうです。「観応の擾乱」以外に「擾乱」って使われているのかしらん?そこは寡聞にしてわからないんです…汗汗
一番わかりやすいのは「役」でしょうか。これは対外戦争を指して使われてますよね。正確に言うと異民族との戦争かな。こっちから仕掛けた場合でも仕掛けられた場合でも異民族との戦争は「役」になってます。元寇は元(モンゴル帝国)が攻めてきたという意味で2回の戦争があり、一度目が「文永の役」二回目が「弘安の役」。モンゴル人は日本人では当然ありませんから。ちなみに平安時代に東北地方を朝廷が侵略した戦争も「前九年の役」と「後三年の役」。つまり当時の東北地方は日本ではなく、住んでいる人も異民族と考えらえていた証拠です。実際東北人は「蝦夷(えみし)」と呼ばれ異民族と考えられていました。この蝦夷(えみし)は「東に住む野蛮人=東夷」からきた言葉であろう、と言われています。そして初めて「日本」が文献に載ったは三国志時代の中国。「魏志倭人伝」は「魏書」の中の「東夷伝」の略称。当時の中国からしたら日本(ヤマタイ=ヤマト?)は「東の島に住む野蛮人=東夷」だったわけです。だから「卑弥呼」という「卑しい」字を女王にも使ってる。本来の意味は「日(の)御子」または「日(の)巫女」だったのではないかとも言われてます。
多分意味的に一番広いのが「乱」でしょうかねえ。でもこれは「反乱」の意味でしょうか。もっと古い時代、神話の時代にもあったでしょうが奈良時代の戦争はほとんどが「乱」でした。恵美押勝にしろ、藤原広嗣にしろ「乱」。どっちも反乱ですもんね。時代は下がって源平の争乱も「乱」。異なる陣営「平氏」と「源氏」の争いでしたが「乱」。これはどちらも一応は「官軍」でしたから「内乱」と見たんでしょうかねえ。ただ勝ったからいいようなものの、最初の源氏の錦の御旗は「以仁王の令旨」。「王」となっていることでわかるように皇位からはかなりかな~り遠いお方。この立場の人が「皇族だから」と「令旨」なんて乱発したらそれこそ「乱」ばっかになりそう。対して平氏にはれっきとした安徳天皇という方がおられた。その後結局、白河法皇に「無し」にされてしまいますが(院政時代ですから上皇、法皇が実権を握っている)、この時点では三種の神器もお持ちになった正式な天皇でしたもんね。
また時代が下がり時代の分かれ目たる「応仁の乱」。これは室町幕府の後継問題ですからやっぱり「内乱」と見たのでしょうか?それにしちゃあ戦争っぽい。けど当時、策謀に長けた東軍筆頭の細川勝元が西軍を「朝敵」にしようと画策、西軍に対して「治罰の綸旨」(天皇家の敵)を出してくれるよう頼みます。けど後花園上皇は「武家同志の私闘である」として綸旨は出しませんでした。つまり朝廷が公式に「武家の内乱」としたんでしょう。だからあれだけの大戦争でも「乱」なんでしょうか。
最後に「変」。これは「薬子の変」など武力を用いても限定的な「クーデター」に使われているような気がします。またまた時代が下がり「本能寺の変」。あれもクーデターですもんね。明智光秀は一万の軍勢を動かしたと言われますが、大兵力どうしのぶつかり合いはその後の秀吉との「山崎の合戦」という「合戦」になってますもんねえ。またまたちなみに明治時代、軍参謀本部で使われていた日本の合戦の解説書によると「関ケ原の合戦」は「関ケ原の役」になっているそうです。「役」ですかあ。。。う~ん、なんでだろう、いままでの説がくずれてしまいそう(汗)
と、色々おもいましたが、どの視点で見て「乱」や「変」、「役」になるのだろう?と考え直すとやっぱり「天皇家から見て」なんじゃないかなあと思い至りました。「本能寺」以降がちょっと微妙ですけど、それは鎌倉はもちろん室町もやっぱ日本の主人は「天皇家」だった証拠かもなあ…と。戦国時代という「何でもあり」になってから変わったのかもなあ…とつい浅知恵。知らないだけで「本能寺」以外の例外もいっぱいあるんでしょうねえ。しかし日本は2000年続いた長~い国なんですねえ。。。そして聞きなれない「擾乱」とは「世を乱し騒がすこと」だそうです。「観応の擾乱」以外に「擾乱」って使われているのかしらん?そこは寡聞にしてわからないんです…汗汗
最もバカげた争乱?観応の擾乱
中公新書から「観応の擾乱」という本が出ました。
今年の初旬から話題になった「応仁の乱」の第二弾という所でしょうか。
高校から中学にかけて最もわかりにくいのはこの南北朝、室町時代です。本当に分かりにくい。南北朝と言うけれど既に室町幕府は開かれていますので南北朝も「室町時代」初期と言えなくもない。しかし室町時代にしちゃうと朝廷より上に武士の政権がきちゃうことになるので南北朝にしたんでしょうかねえ??とにかく学生時代は最も嫌いな時代でした。ところが今は大好き(笑)日本の最悪な所と良い伝統?がぶつかり合ってるように見える、それが室町時代に感じるんですよねえ。「応仁の乱」も最初は
将軍の息子 足利義尚・山名宗全 VS 将軍の弟 足利義視(よしみ)・細川勝元
で始まりましたが結局
将軍の息子 足利義尚・細川勝元 VS 将軍の弟 足利義視・山名宗全
になっちゃいます。東軍が細川勝元で西軍が山名宗全で始まり、最後にはそれぞれが推す次期将軍が逆になってしまいます。なんでこうなるの?最大の理由は現将軍である義政。乱の最初から東軍側にいたけど「いた」だけで跡継ぎを決めなかった。乱が拡大してからも次期将軍を決めませんでした。が、結局最後は息子の義尚に将軍を譲る。もう長年戦ってきた西軍は引くに引け無くなって義視を「将軍格」として迎え戦い続けた…。そもそも義政は現将軍なんだから最初から鶴の一声で「息子を将軍にする」と言えば済むのにそれができなかった。
なんでかちゅーと義政は「俺はめんどくさい将軍なんか止める」と言い出し、比叡山の高僧であった弟の義視を還俗させて無理やり次期将軍として立てたからです。義視は御台所、つまり義政の妻 日野富子がまだ若く「子供ができたらどうするのか」と兄に問いただします。すると「子供ができたら出家させて僧にする。お前が将軍だ」
でも、そう言われてもすぐには信用できない。結局息子が可愛いってことになるんじゃないかと。。。そのため義視は保証人を求めます。それが細川勝元。大大名で管領を務める細川勝元が後見人になることで、やっと義視は還俗することを決めました。このまま行けば当然、乱(戦争)なんて起きないはずでした。
もちろん、このままでは済みませんで、富子が男の子を産んだのです。富子は当然実子の義尚を将軍にしたい。僧になんかしたくない。「あーた、息子が可愛くないの⁉」妻である富子に追い詰められ「義視(弟)を将軍にする」とどうしても言えなくなってしまった。富子も息子 義尚の為に後見人を求めました。それが中国地方に一大勢力を持つ大大名の山名宗全。
二つの権威(弟 義視、息子 義尚)に武力(山名宗全、細川勝元)が結びつきました。これはいつか戦争にならざるを得ません。…という見方はシロウト。本当はもっと複雑であるというのが御座勇一「応仁の乱」です。シロウトが乱の原因は将軍後継問題というのは良いが、研究者にとってはそんな単純なものではない、と。実際、乱の始まりは畠山政長(おい)と畠山義就(おじ)との骨肉の合戦から始まってますけど、これが結構複雑。(「御霊合戦」)つまり他の大名の相続争い、悪党(新しい勢力)と旧勢力の対立、国一揆、土民一揆、仏教寺院同志の対立などなど~複雑で無茶苦茶な時代なんです。わかりにくくても仕方ないですよねえ…。高校日本史の1時間授業では到底無理です(自分の時は応仁の乱は1時間でしたので)
でもやっぱりこの乱の全ては現将軍だった義政だと思います。「大御所(引退した将軍)になって自分の趣味に浸りつくしたい」その為に弟を将軍にしようとした事、それを徹底できなかった(実子義尚が生まれてしまった)事、将軍後継問題をズルズル引っ張ってしまった事にあるんだと思います。義政はとんでもない将軍でしたもんね。当時大飢饉中だった京都で大々的に酒宴を催したり、餓死者が累々と横たわる京都を横目に花見の宴を開いたり…。その上に別荘を建てたり能、狂言に戯れます。しかし皮肉なことにこれが「東山文化」になるんですよねえ。日本の美とも言える陰影の美はここからとも言える。本当に皮肉なことです…。
この応仁の乱に負けず劣らないのが今度本が出た「観応の擾乱」です。室町初期のこの乱?は結果がすごいバカげてる…って長くなったので今はここで打ち切りです。。。なにせ今度?は南北朝もからんで来ますから(汗)…思えば、有名な「乱」というのは多くが「跡継ぎ問題」。つまりは骨肉の争いっちゅー悲しい歴史ですね…。。。日本史好き男の思いひとしおですねえ。。。
PS 応仁の乱最初の合戦「御霊合戦」 御霊神社で行われたこの合戦も畠山家の内乱。叔父と甥の戦いで一方が畠山政長、もう一方が畠山義就(よしなり)と自分は習いました。でも「応仁の乱」を読んだら畠山義就(よしひろ)となってました。どうやら「よしなり」でも「よしひろ」でもどちらでも良いようなのですが、最近読んだ本はほとんど「よしひろ」。「よしなり」で覚えている自分はなんとなくしっくり来ないんですよねえ「よしひろ」(苦笑)
今年の初旬から話題になった「応仁の乱」の第二弾という所でしょうか。
高校から中学にかけて最もわかりにくいのはこの南北朝、室町時代です。本当に分かりにくい。南北朝と言うけれど既に室町幕府は開かれていますので南北朝も「室町時代」初期と言えなくもない。しかし室町時代にしちゃうと朝廷より上に武士の政権がきちゃうことになるので南北朝にしたんでしょうかねえ??とにかく学生時代は最も嫌いな時代でした。ところが今は大好き(笑)日本の最悪な所と良い伝統?がぶつかり合ってるように見える、それが室町時代に感じるんですよねえ。「応仁の乱」も最初は
将軍の息子 足利義尚・山名宗全 VS 将軍の弟 足利義視(よしみ)・細川勝元
で始まりましたが結局
将軍の息子 足利義尚・細川勝元 VS 将軍の弟 足利義視・山名宗全
になっちゃいます。東軍が細川勝元で西軍が山名宗全で始まり、最後にはそれぞれが推す次期将軍が逆になってしまいます。なんでこうなるの?最大の理由は現将軍である義政。乱の最初から東軍側にいたけど「いた」だけで跡継ぎを決めなかった。乱が拡大してからも次期将軍を決めませんでした。が、結局最後は息子の義尚に将軍を譲る。もう長年戦ってきた西軍は引くに引け無くなって義視を「将軍格」として迎え戦い続けた…。そもそも義政は現将軍なんだから最初から鶴の一声で「息子を将軍にする」と言えば済むのにそれができなかった。
なんでかちゅーと義政は「俺はめんどくさい将軍なんか止める」と言い出し、比叡山の高僧であった弟の義視を還俗させて無理やり次期将軍として立てたからです。義視は御台所、つまり義政の妻 日野富子がまだ若く「子供ができたらどうするのか」と兄に問いただします。すると「子供ができたら出家させて僧にする。お前が将軍だ」
でも、そう言われてもすぐには信用できない。結局息子が可愛いってことになるんじゃないかと。。。そのため義視は保証人を求めます。それが細川勝元。大大名で管領を務める細川勝元が後見人になることで、やっと義視は還俗することを決めました。このまま行けば当然、乱(戦争)なんて起きないはずでした。
もちろん、このままでは済みませんで、富子が男の子を産んだのです。富子は当然実子の義尚を将軍にしたい。僧になんかしたくない。「あーた、息子が可愛くないの⁉」妻である富子に追い詰められ「義視(弟)を将軍にする」とどうしても言えなくなってしまった。富子も息子 義尚の為に後見人を求めました。それが中国地方に一大勢力を持つ大大名の山名宗全。
二つの権威(弟 義視、息子 義尚)に武力(山名宗全、細川勝元)が結びつきました。これはいつか戦争にならざるを得ません。…という見方はシロウト。本当はもっと複雑であるというのが御座勇一「応仁の乱」です。シロウトが乱の原因は将軍後継問題というのは良いが、研究者にとってはそんな単純なものではない、と。実際、乱の始まりは畠山政長(おい)と畠山義就(おじ)との骨肉の合戦から始まってますけど、これが結構複雑。(「御霊合戦」)つまり他の大名の相続争い、悪党(新しい勢力)と旧勢力の対立、国一揆、土民一揆、仏教寺院同志の対立などなど~複雑で無茶苦茶な時代なんです。わかりにくくても仕方ないですよねえ…。高校日本史の1時間授業では到底無理です(自分の時は応仁の乱は1時間でしたので)
でもやっぱりこの乱の全ては現将軍だった義政だと思います。「大御所(引退した将軍)になって自分の趣味に浸りつくしたい」その為に弟を将軍にしようとした事、それを徹底できなかった(実子義尚が生まれてしまった)事、将軍後継問題をズルズル引っ張ってしまった事にあるんだと思います。義政はとんでもない将軍でしたもんね。当時大飢饉中だった京都で大々的に酒宴を催したり、餓死者が累々と横たわる京都を横目に花見の宴を開いたり…。その上に別荘を建てたり能、狂言に戯れます。しかし皮肉なことにこれが「東山文化」になるんですよねえ。日本の美とも言える陰影の美はここからとも言える。本当に皮肉なことです…。
この応仁の乱に負けず劣らないのが今度本が出た「観応の擾乱」です。室町初期のこの乱?は結果がすごいバカげてる…って長くなったので今はここで打ち切りです。。。なにせ今度?は南北朝もからんで来ますから(汗)…思えば、有名な「乱」というのは多くが「跡継ぎ問題」。つまりは骨肉の争いっちゅー悲しい歴史ですね…。。。日本史好き男の思いひとしおですねえ。。。
PS 応仁の乱最初の合戦「御霊合戦」 御霊神社で行われたこの合戦も畠山家の内乱。叔父と甥の戦いで一方が畠山政長、もう一方が畠山義就(よしなり)と自分は習いました。でも「応仁の乱」を読んだら畠山義就(よしひろ)となってました。どうやら「よしなり」でも「よしひろ」でもどちらでも良いようなのですが、最近読んだ本はほとんど「よしひろ」。「よしなり」で覚えている自分はなんとなくしっくり来ないんですよねえ「よしひろ」(苦笑)
キャリー(2013年版)を観ました。
キャリー(2013年版)を観ました。
コミケが落ちたのでDVD、Brayを借りてホラー三昧。キャリーは2013年版と1978年版があり両方見比べ。というより1978年版はもともとDVDを持っています。ただ新しく再版されたものには日本語吹き替えがありそれ目当て、だったのですが、日本語の吹替のない旧版を借りてきてしまったようです。う~ん、初歩的なミス。これなら借りなくてもよかったし(汗)
ーーーー以下ネタバレありーーーー
リメイクされると新しい展開が導入されるのが普通ですがこのキャリー・リメイクはほとんど原作と同じ。ちょっと派手になったかな~ってくらいのもの。もはやホラーの金字塔?である映画なのであらすじ書かなくても大丈夫かと思いますが、一応。
高校でいじめられっ子のキャリー。体育の授業の後、シャワー中に生理がくる。キャリーは驚きパニック。周りの生徒ははやし立てタンポンナプキンを投げつける(いじめ)。それに気が付いた体育教師リタはパニクるキャリーをビンタ。キャリーは月経の事を何も知らなかったようだ。校長室に呼ばれるキャリー。キャリーの母親マーガレットは狂信的なキリスト教徒。月経や男女交際を罪、汚れたものとして教えていなかった。校長は今回の事を母親に知らせるという。反射的にキャリーが反抗すると灰皿が飛ぶ(78年版)ウォータークーラーが割れる(2013年版)。家に帰るとキャリーは月経の事で「汚れた罪」をしたとして物置に閉じ込められる。その時、自分の怒りにより物置の扉にヒビが入る。「自分には特別な力がある」と気づいたキャリー。
リタはシャワー室のいじめに参加した生徒に特別メニューをこなさなければプロム(卒業パーティ)に参加させないと宣言。ほとんどの生徒がメニューをこなす中、クリスだけが反発。結局クリスだけがプロムに参加できなくなる。クリスはキャリーのせいだと逆恨み、プロムでキャリーに恥をかかす計画を練る。シャワー室のいじめに参加したスーは良心の呵責から自分の恋人であるトミーにキャリーをプロムに誘うよう頼む。キャリーははじめて男の子に誘われ始めてのデートがプロム。それを知った母マーガレットは「神の怒りを買うぞ」と猛反対。そんな母をキャリーは「力」で封じ込め、あこがれのトミーとプロムへ行くのだった…。
ここからはあの有名なプロム・クイーンに選ばれ壇上に仕掛けられたブタの血をかぶせられる。パニックになったキャリーは「力」を開放し無差別に生徒たちを殺し始める…というシーン。ラストもほぼ同じ…ですが、キャリーの墓から手が出るシーン、それは夢だったシーンが2013年版にはありません。
いままで何回も書いてきましたが、自分はリメイクが好きです。30年前の感性を現代の感性で解釈するのはとても面白いと思うから。でも一方リメイク許さないという人の気持ちもわからなくはないです。今回のキャリー・リメイクはそういう思いの自分からしたら0点です。だって何から何まで同じすぎます。だったらあのブライアン・デ・パルマ演出の78版の方がはるかに良い。パルマの秀悦なミステリータッチ、エロティシズムがまったく消えてしまっている。エロといえば「つかみの全裸」(出だしのシャワーシーンで)が2013年版には無いですが、そんなこっちゃどーでもいいです(あってほしかったですけど)プロムでいじめっ子のクリスがキャリーにブタの血をかけようとするシーン。あの緊張感、サスペンス感、唇をなめるエロティシズ。、そういう構成が無いんですもん。パルマ調でなくていいからそこはもっと頑張って欲しかった。
ーーーーーーーーーー
「これはリメイク作るべきじゃなかった」リメイク好きの自分がそう思いました。
そうだなあ…「つかみの全裸」でクロエ・グレース・モレッツが全裸を披露してたら「うん、まあいいか!」になってたかも(笑)ただクロエはちょっと美人すぎ。シシー・スペイセクくらい個性的な感じじゃないといじめられっ子っぽくないかなあとも思いました。ただ一つ今回のリメイクで良かったのは「クロエ・キャリー」の反応が日本人好みな感じでかわいい。
クロエ・グレース・モレッツは「モールス」「キック・アス」ともに個性的ですが(演出のせいか)キャリーは微妙かなあ。ちなみにこの2本どっちも好きな映画です。
PS この「キャリー」以後、スティーブン・キング原作の映画は売れないと言われていたと聞いた事があります。それを打ち破ったのが「ペット・セメタリー」だったか「ミザリー」だったか。多分「ミザリー」。アカデミー主演女優賞なのですごい売れたと思います。「ペット・セメタリー」は原作愛好家が確か「原作の雰囲気がない」と酷評してたと思うので。。。「ミザリー」も原作と違うようですが主演のキャシー・ベイツの演技がそれを吹き飛ばした感じです。
小説の映画化に伴う「原作と違う」批判。これ難しいですよねえ…。原作読んでない自分は「ペット・セメタリー」も十分楽しめました。思えばキングで原作読んでいるのは「IT」と「ゴールデンボーイ」あとは「ファントム」…はD・R・クーンツか(バケモノ設定がすごい「IT]に似てるんですよね)あ、「シャイニング」も読みました。映画見てから友人に「小説は全然違うし、もっとすごい」と言われて。でも先に映画を見たせいかそれほどでもありませんでした。確かに映画では題名の「シャイニング」の意味がものすごく薄くなってます。まあキューブリックのこの映画が気に入らずキング自ら真「シャイニング」をTV映画として撮っている有名な「原作と違う」映画ですから(苦笑)でもキューブリックの代表作に必ず入る映画なんですよねえ…。
コミケが落ちたのでDVD、Brayを借りてホラー三昧。キャリーは2013年版と1978年版があり両方見比べ。というより1978年版はもともとDVDを持っています。ただ新しく再版されたものには日本語吹き替えがありそれ目当て、だったのですが、日本語の吹替のない旧版を借りてきてしまったようです。う~ん、初歩的なミス。これなら借りなくてもよかったし(汗)
ーーーー以下ネタバレありーーーー
リメイクされると新しい展開が導入されるのが普通ですがこのキャリー・リメイクはほとんど原作と同じ。ちょっと派手になったかな~ってくらいのもの。もはやホラーの金字塔?である映画なのであらすじ書かなくても大丈夫かと思いますが、一応。
高校でいじめられっ子のキャリー。体育の授業の後、シャワー中に生理がくる。キャリーは驚きパニック。周りの生徒ははやし立てタンポンナプキンを投げつける(いじめ)。それに気が付いた体育教師リタはパニクるキャリーをビンタ。キャリーは月経の事を何も知らなかったようだ。校長室に呼ばれるキャリー。キャリーの母親マーガレットは狂信的なキリスト教徒。月経や男女交際を罪、汚れたものとして教えていなかった。校長は今回の事を母親に知らせるという。反射的にキャリーが反抗すると灰皿が飛ぶ(78年版)ウォータークーラーが割れる(2013年版)。家に帰るとキャリーは月経の事で「汚れた罪」をしたとして物置に閉じ込められる。その時、自分の怒りにより物置の扉にヒビが入る。「自分には特別な力がある」と気づいたキャリー。
リタはシャワー室のいじめに参加した生徒に特別メニューをこなさなければプロム(卒業パーティ)に参加させないと宣言。ほとんどの生徒がメニューをこなす中、クリスだけが反発。結局クリスだけがプロムに参加できなくなる。クリスはキャリーのせいだと逆恨み、プロムでキャリーに恥をかかす計画を練る。シャワー室のいじめに参加したスーは良心の呵責から自分の恋人であるトミーにキャリーをプロムに誘うよう頼む。キャリーははじめて男の子に誘われ始めてのデートがプロム。それを知った母マーガレットは「神の怒りを買うぞ」と猛反対。そんな母をキャリーは「力」で封じ込め、あこがれのトミーとプロムへ行くのだった…。
ここからはあの有名なプロム・クイーンに選ばれ壇上に仕掛けられたブタの血をかぶせられる。パニックになったキャリーは「力」を開放し無差別に生徒たちを殺し始める…というシーン。ラストもほぼ同じ…ですが、キャリーの墓から手が出るシーン、それは夢だったシーンが2013年版にはありません。
いままで何回も書いてきましたが、自分はリメイクが好きです。30年前の感性を現代の感性で解釈するのはとても面白いと思うから。でも一方リメイク許さないという人の気持ちもわからなくはないです。今回のキャリー・リメイクはそういう思いの自分からしたら0点です。だって何から何まで同じすぎます。だったらあのブライアン・デ・パルマ演出の78版の方がはるかに良い。パルマの秀悦なミステリータッチ、エロティシズムがまったく消えてしまっている。エロといえば「つかみの全裸」(出だしのシャワーシーンで)が2013年版には無いですが、そんなこっちゃどーでもいいです(あってほしかったですけど)プロムでいじめっ子のクリスがキャリーにブタの血をかけようとするシーン。あの緊張感、サスペンス感、唇をなめるエロティシズ。、そういう構成が無いんですもん。パルマ調でなくていいからそこはもっと頑張って欲しかった。
ーーーーーーーーーー
「これはリメイク作るべきじゃなかった」リメイク好きの自分がそう思いました。
そうだなあ…「つかみの全裸」でクロエ・グレース・モレッツが全裸を披露してたら「うん、まあいいか!」になってたかも(笑)ただクロエはちょっと美人すぎ。シシー・スペイセクくらい個性的な感じじゃないといじめられっ子っぽくないかなあとも思いました。ただ一つ今回のリメイクで良かったのは「クロエ・キャリー」の反応が日本人好みな感じでかわいい。
クロエ・グレース・モレッツは「モールス」「キック・アス」ともに個性的ですが(演出のせいか)キャリーは微妙かなあ。ちなみにこの2本どっちも好きな映画です。
PS この「キャリー」以後、スティーブン・キング原作の映画は売れないと言われていたと聞いた事があります。それを打ち破ったのが「ペット・セメタリー」だったか「ミザリー」だったか。多分「ミザリー」。アカデミー主演女優賞なのですごい売れたと思います。「ペット・セメタリー」は原作愛好家が確か「原作の雰囲気がない」と酷評してたと思うので。。。「ミザリー」も原作と違うようですが主演のキャシー・ベイツの演技がそれを吹き飛ばした感じです。
小説の映画化に伴う「原作と違う」批判。これ難しいですよねえ…。原作読んでない自分は「ペット・セメタリー」も十分楽しめました。思えばキングで原作読んでいるのは「IT」と「ゴールデンボーイ」あとは「ファントム」…はD・R・クーンツか(バケモノ設定がすごい「IT]に似てるんですよね)あ、「シャイニング」も読みました。映画見てから友人に「小説は全然違うし、もっとすごい」と言われて。でも先に映画を見たせいかそれほどでもありませんでした。確かに映画では題名の「シャイニング」の意味がものすごく薄くなってます。まあキューブリックのこの映画が気に入らずキング自ら真「シャイニング」をTV映画として撮っている有名な「原作と違う」映画ですから(苦笑)でもキューブリックの代表作に必ず入る映画なんですよねえ…。