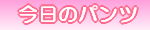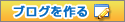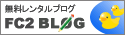「涼宮ハルヒの憂鬱」
ずっとアニメを観ていなかった自分がアニメを再び観るようになったのは「涼宮ハルヒの憂鬱」からでした。
某先生に「次はこれが流行ると思う」と聞いたのがきっかけでまず小説を読みました。それもまた最近のラノベを読んだ最初です。
思えば朝日ソノラマ「オペレーション・MMシリーズ」以来のアニメ系?SFだったかも知れません。
そして「ハルヒ」にハマリましたねえ。小さい頃NHKで「少年SFドラマ劇場」(名前はうろ覚え)というものがあり夢中で見ていた記憶があります。内容はほとんど忘れてしまいましたが雰囲気だけは覚えていました。「ハルヒ」にはその雰囲気を感じたんですよね。ハマった理由はこれでしょう。中学生になって図書館の眉村卓作品を読みまたハマリましたがその雰囲気も感じました。
確か「少年SFドラマ劇場」でも眉村卓の「閉ざされた時間割」などあったかもしれません。あ、「謎の転校生」はドラマ化してたような。。。よく覚えてないけど「栄光塾」が出てきたような。。。
そういえば「ねらわれた学園」の映画をどきどきしながら見ましたが全然違う話でショックを受けたのもこの頃だった・・・かな?と思います。最初の小説では題名が違っていたんですよね。
ともかく「ハルヒ」はそんな中二時代を思い出させるんです。田舎の中学で育った自分は中学時代にいい思い出はありませんがラノベ当時は「ジュブナイル」の世界に一番ハマっていた時代でした。その雰囲気だけは今でも好きです。
ですのでハルヒが中途で終わって?しまっているのは少々残念。でもあの話は続くと難しいと思います。なぜなら主人公のハルヒがSF的冒険ができない設定になってますから。(ハルヒが超常的体験をしてしまうと世界が変わってしまうから)でもハルヒとキョンの今後の関係はちょっと読んでみたかったかな。
しかしSFはこの時代まで。その後自分はRPG的剣と魔法の時代になります。この時代もまた大好きなんですよね(笑)今でも剣と魔法は描きたいですねえ。
某先生に「次はこれが流行ると思う」と聞いたのがきっかけでまず小説を読みました。それもまた最近のラノベを読んだ最初です。
思えば朝日ソノラマ「オペレーション・MMシリーズ」以来のアニメ系?SFだったかも知れません。
そして「ハルヒ」にハマリましたねえ。小さい頃NHKで「少年SFドラマ劇場」(名前はうろ覚え)というものがあり夢中で見ていた記憶があります。内容はほとんど忘れてしまいましたが雰囲気だけは覚えていました。「ハルヒ」にはその雰囲気を感じたんですよね。ハマった理由はこれでしょう。中学生になって図書館の眉村卓作品を読みまたハマリましたがその雰囲気も感じました。
確か「少年SFドラマ劇場」でも眉村卓の「閉ざされた時間割」などあったかもしれません。あ、「謎の転校生」はドラマ化してたような。。。よく覚えてないけど「栄光塾」が出てきたような。。。
そういえば「ねらわれた学園」の映画をどきどきしながら見ましたが全然違う話でショックを受けたのもこの頃だった・・・かな?と思います。最初の小説では題名が違っていたんですよね。
ともかく「ハルヒ」はそんな中二時代を思い出させるんです。田舎の中学で育った自分は中学時代にいい思い出はありませんがラノベ当時は「ジュブナイル」の世界に一番ハマっていた時代でした。その雰囲気だけは今でも好きです。
ですのでハルヒが中途で終わって?しまっているのは少々残念。でもあの話は続くと難しいと思います。なぜなら主人公のハルヒがSF的冒険ができない設定になってますから。(ハルヒが超常的体験をしてしまうと世界が変わってしまうから)でもハルヒとキョンの今後の関係はちょっと読んでみたかったかな。
しかしSFはこの時代まで。その後自分はRPG的剣と魔法の時代になります。この時代もまた大好きなんですよね(笑)今でも剣と魔法は描きたいですねえ。
昔のアニメ・・・「舞-HiME」シリーズ
昔のアニメを観ました。「舞-HiME」(2004)続く(?)「舞-乙HiME」(2005)
2004~2005年といえば「ガンダム世代」の自分からするとつい最近な気がしますが、もはや10年前。一昔と呼称される期間です。
でも今更ながらこの時代のアニメは好きですねえ・・・ってこの2作品もリアルタイムでは観ていなかったんですけど。「舞-HIME」シリーズはちょうどアニメ・マンガをほとんど観てない時期にあたります。自分は影響を受けやすく(受けても下手なので他人からはよくわからなかったりしますが)面白いと思ったものはマネしたくなるんですよねえ。ですので流行りのものはあまり観ないようにしたりする事がしばしば。そしてあまり流行らなくなった頃に観て「面白い~」ということばっかりです。よく考えると(いや、よく考えなくても)時代に完全に乗り遅れてますね・・・そういえば「艦これ」もそうです。
「舞-HiME」のキャッチフレーズは「サンライズ初の萌えアニメ」というらしいのですがあんまり「萌え」ではない様な。孤島にある風華学園に高次具現化能力を持つ女の子が集まり己の存在をかけて戦うという物語。勝ち残った女の子は其の地で世界を変える存在となる。主人公は転校してきた明るくも不幸な16歳ときは舞。なんかやっぱり自分が思ってる萌えとは違う気がしました。ただ「萌え」の定義がイマイチよくわかっていませんで、個人的には「がくえんゆーとぴあ まなびストレート!」みたいなのを言うのかと(勝手な思い込みです。。。間違ってたらすみません)ゲームの「萌え萌え第二次世界大戦~chu」というのも最近知ったのですがなんとなくそんな感じに・・・(やってないので見た目の感想ですが)ともあれ、後半はハードな話でラストはアニメらしく大団円という流れ。これ好きでした。やっぱハッピーエンドがいいですなあ~現実が苦しいだけに(涙)
続く「舞-乙HiME」は基本キャラクターは同じなのですがまったく別物。はるか未来、別の惑星に移り住んだ人類はその惑星で栄枯盛衰を繰り返し戦いの悲惨さを弱めるために高次具現化能力をもつオトメの戦いに国の存亡をかけるようになる。オトメは男性を知らない乙女にしかなることはできずそのオトメを育てる専門学校ガルデローベ学園での一人の少女アリカ・ユメミヤの物語。ラストはやはりサンライズらしく国家、世界をかけた戦いに発展していく。
これって「リリカルなのは」に触発されたスタッフがいわばサンライズ版「なのは」をつくりたくて製作したとか聞きました。嘘か真か、言われてみれば似てなくもないような。。。「なのは」はいまだに健在で「ビビオ」になっていますが「舞-乙HiME」はOVAが出たりしてけっこう長く続きました。
・・・とは言うものの、個人的には断然「舞-HiME」の方がはるかにはるかに好きです、雰囲気もストーリーも。出来れば「舞-HiME」の方を続けて欲しかった(笑)でもあのラストで完結状態なので続編を作るのは難しいでしょうけど。だからこそキャラクターは同じで別の話となったのでしょうねえ。{オーディオドラマ(ラジオドラマ?)は出ましたが・・・}
と、言いながら「舞-乙HiME」は続編のOVAが大好きでした。「舞-乙HiME Zwei 」TV版から1年後、惑星間戦略兵器が落ちてくる話。「舞-乙HiME 0〜S.ifr(シフル)」TV版主人公アリカのお母さんレナの話。どっちもおもしろかった。特に「S.ifr(シフル)」は好きで続編を期待しましたが作られずがっかり。ストーリー構成も明らかに続編があるような感じになっているのに・・・売れなかったんでしょうか?
実際TVシリーズもつまらなくはなかったのですがOVAのほうがはるかに好き。個人的にOVAだけで十分とも・・・ですが、本編観てないと結局理解不能なんですけど。。。実はいまだに「S.ifr(シフル)」の続編がつくられないかな・・・と希望、期待中です。。。
思えば「ガンダム」以来、再び本格的にアニメに戻してくれたのは「ハルヒ」だったかもしれません。それ以前のアニメは機会があれば現在でも観る様にしています。同人描きたかったなあという思いも今頃・・・ですねえ。
2004~2005年といえば「ガンダム世代」の自分からするとつい最近な気がしますが、もはや10年前。一昔と呼称される期間です。
でも今更ながらこの時代のアニメは好きですねえ・・・ってこの2作品もリアルタイムでは観ていなかったんですけど。「舞-HIME」シリーズはちょうどアニメ・マンガをほとんど観てない時期にあたります。自分は影響を受けやすく(受けても下手なので他人からはよくわからなかったりしますが)面白いと思ったものはマネしたくなるんですよねえ。ですので流行りのものはあまり観ないようにしたりする事がしばしば。そしてあまり流行らなくなった頃に観て「面白い~」ということばっかりです。よく考えると(いや、よく考えなくても)時代に完全に乗り遅れてますね・・・そういえば「艦これ」もそうです。
「舞-HiME」のキャッチフレーズは「サンライズ初の萌えアニメ」というらしいのですがあんまり「萌え」ではない様な。孤島にある風華学園に高次具現化能力を持つ女の子が集まり己の存在をかけて戦うという物語。勝ち残った女の子は其の地で世界を変える存在となる。主人公は転校してきた明るくも不幸な16歳ときは舞。なんかやっぱり自分が思ってる萌えとは違う気がしました。ただ「萌え」の定義がイマイチよくわかっていませんで、個人的には「がくえんゆーとぴあ まなびストレート!」みたいなのを言うのかと(勝手な思い込みです。。。間違ってたらすみません)ゲームの「萌え萌え第二次世界大戦~chu」というのも最近知ったのですがなんとなくそんな感じに・・・(やってないので見た目の感想ですが)ともあれ、後半はハードな話でラストはアニメらしく大団円という流れ。これ好きでした。やっぱハッピーエンドがいいですなあ~現実が苦しいだけに(涙)
続く「舞-乙HiME」は基本キャラクターは同じなのですがまったく別物。はるか未来、別の惑星に移り住んだ人類はその惑星で栄枯盛衰を繰り返し戦いの悲惨さを弱めるために高次具現化能力をもつオトメの戦いに国の存亡をかけるようになる。オトメは男性を知らない乙女にしかなることはできずそのオトメを育てる専門学校ガルデローベ学園での一人の少女アリカ・ユメミヤの物語。ラストはやはりサンライズらしく国家、世界をかけた戦いに発展していく。
これって「リリカルなのは」に触発されたスタッフがいわばサンライズ版「なのは」をつくりたくて製作したとか聞きました。嘘か真か、言われてみれば似てなくもないような。。。「なのは」はいまだに健在で「ビビオ」になっていますが「舞-乙HiME」はOVAが出たりしてけっこう長く続きました。
・・・とは言うものの、個人的には断然「舞-HiME」の方がはるかにはるかに好きです、雰囲気もストーリーも。出来れば「舞-HiME」の方を続けて欲しかった(笑)でもあのラストで完結状態なので続編を作るのは難しいでしょうけど。だからこそキャラクターは同じで別の話となったのでしょうねえ。{オーディオドラマ(ラジオドラマ?)は出ましたが・・・}
と、言いながら「舞-乙HiME」は続編のOVAが大好きでした。「舞-乙HiME Zwei 」TV版から1年後、惑星間戦略兵器が落ちてくる話。「舞-乙HiME 0〜S.ifr(シフル)」TV版主人公アリカのお母さんレナの話。どっちもおもしろかった。特に「S.ifr(シフル)」は好きで続編を期待しましたが作られずがっかり。ストーリー構成も明らかに続編があるような感じになっているのに・・・売れなかったんでしょうか?
実際TVシリーズもつまらなくはなかったのですがOVAのほうがはるかに好き。個人的にOVAだけで十分とも・・・ですが、本編観てないと結局理解不能なんですけど。。。実はいまだに「S.ifr(シフル)」の続編がつくられないかな・・・と希望、期待中です。。。
思えば「ガンダム」以来、再び本格的にアニメに戻してくれたのは「ハルヒ」だったかもしれません。それ以前のアニメは機会があれば現在でも観る様にしています。同人描きたかったなあという思いも今頃・・・ですねえ。
「ヒート」と「悪魔」
今日は少々ムシムシしてます。
悲しいかな、暇ですので色々考えられる時間があり(しかしその多くがマイナスな事ですが)その為ブログを更新する機会も増える結果となっております。
「ヒート」という映画がありました。1995年マイケル・マン監督の映画です。個人的にですけどマイケル・マン監督作品ってあまり好みではないのですがなぜか「ヒート」だけは大好きでDVDもすぐ買いました。日曜洋画劇場の淀川長治の解説では出演のロバート・デ・ニーロとアル・パチーノが不仲で同時撮影を拒んだとか。実際、映画の中でも二人のシーンはほとんどどちらかが後姿になっていて「ほんとに競演してるのかいな?」と疑問が生じるほどです。なんせ感動的であるラストでさえ一人は完全な後姿なんですから(多分一人一人別撮りして後に編集でつなげている)唯一二人で写ってるだろうと思えるのは途中でのカフェのシーンだけだと思います。その後、競演した映画ではちゃんと二人で写っているようですからこの時だけはすごい不仲だったんですかねえ??
で、この名優二人はそれぞれ「悪魔」役をやっております。デ・ニーロは「エンゼル・ハート」(1987)パチーノは「ディアボロス」(1997)奇しくも10年差での役ですがそれぞれの特色が出ていた悪魔役だったような気がします。もちろん映画の色がありますがそれに合わせた配役ですので俳優の色とも言えるのではないかと。デ・ニーロは「畏怖の魔王」パチーノは「背徳の魔王」という感じが見事に出ていたと思います。なるほど・・・なんとなくソリが合わなそうですね(苦笑)
どちらも「ルシフェル」役なのですが解釈は違えど最強の「堕天使」名優にふさわしい役なのかも。
悲しいかな、暇ですので色々考えられる時間があり(しかしその多くがマイナスな事ですが)その為ブログを更新する機会も増える結果となっております。
「ヒート」という映画がありました。1995年マイケル・マン監督の映画です。個人的にですけどマイケル・マン監督作品ってあまり好みではないのですがなぜか「ヒート」だけは大好きでDVDもすぐ買いました。日曜洋画劇場の淀川長治の解説では出演のロバート・デ・ニーロとアル・パチーノが不仲で同時撮影を拒んだとか。実際、映画の中でも二人のシーンはほとんどどちらかが後姿になっていて「ほんとに競演してるのかいな?」と疑問が生じるほどです。なんせ感動的であるラストでさえ一人は完全な後姿なんですから(多分一人一人別撮りして後に編集でつなげている)唯一二人で写ってるだろうと思えるのは途中でのカフェのシーンだけだと思います。その後、競演した映画ではちゃんと二人で写っているようですからこの時だけはすごい不仲だったんですかねえ??
で、この名優二人はそれぞれ「悪魔」役をやっております。デ・ニーロは「エンゼル・ハート」(1987)パチーノは「ディアボロス」(1997)奇しくも10年差での役ですがそれぞれの特色が出ていた悪魔役だったような気がします。もちろん映画の色がありますがそれに合わせた配役ですので俳優の色とも言えるのではないかと。デ・ニーロは「畏怖の魔王」パチーノは「背徳の魔王」という感じが見事に出ていたと思います。なるほど・・・なんとなくソリが合わなそうですね(苦笑)
どちらも「ルシフェル」役なのですが解釈は違えど最強の「堕天使」名優にふさわしい役なのかも。
「逆説の日本史 近世展開編」を読みました
最近暖かくなって微妙な日々。5月という月は自分にとっては印象深い月でもあります。ペンネームを変えた月でもあるんです。以前住んでいた所に藤の花が有名な社がありました。おばあちゃんはそこの氏子でした。当時売れないのでそれにちなんだペンネームに変えたんですよね。でも・・・この季節は毎年あまり良い印象がありません。萌え出づるこの季節、毎年暗くなるんです・・・。
。。。。以下、長いしすごい趣味の分野なので飛ばしておkだと思います。。。。
「逆説の日本史 近世展開編」を読みました。作家の井沢元彦の本には大変影響を受けました。エスカリテ文庫の各宗教の本(「密教の本」とか「神道の本」)を読んで井沢元彦の「世界宗教講座」を読むと「なるほど宗教って」と思います。井沢元彦のライフワークであるという「逆説の日本史」もとびとびで全部は読んでないですけど日本史というものを理解させてくれました。・・・ただ、井沢元彦自身が「荒い捉え方でもあるかもしれない」と言っている通り「むむ?」と思う事もあります。
ビンボーの中、古本屋で「逆説の日本史 近世展開編」を買いました。キリスト教や島原の乱を経ていかに日本が鎖国したかが解き明かされていました。「鎖国法という法はなく日本の鎖国はキリスト教禁令からの成り行きでなし崩しになされたもの」「徳川家康はキリスト教禁令は命じたが、むしろヨーロッパとの貿易には積極的だった」「ゆえに幕末、維新の志士が鎖国はこの国の定法と思っていたのは誤解で家康に従えば開国が本音だった」というのはけっこう目からウロコでした。しかし「このなし崩しの決定は歴史的に観て情報を軽視した江戸幕府(日本)独自の考えでバカだった」というような感じは「むむ?」と思いました。当時の世界の国家で本当に最初から情報をもって計画的に「進出」していた国家ってあったのかいな?ヨーロッパの進出もなんとなく「なし崩し」じゃないのかしらん?比較にそのあたりを出してもらえないと何とも言えないような・・・。ヨーロッパって結果成功してるから「正しかった」ってなってないかしら?とも思うのです。むしろ日本は井沢氏おっしゃるところの「和の精神」に忠実だからこそ「なし崩し」に見えるのではないかなあ?と思ったり・・・。だって大名統制は「由比正雪の乱」までは徹底して変えなかった、と他方では言ってるんだしなんか整合性が・・・と思ったりしました。
しかしこれはつまり日本は「情報に昔から疎い」ということをおっしゃてるのでしょう。もっと言うなら「情報を軽視する」という日本の伝統?があると。これは現代にまで続く日本の欠点、いや弱点だと思います。大東亜戦争でも欧米軍の充分な情報を集めずに中国軍に対するのと同じ戦法で戦い、大きな被害を出したといいます。(ちなみにすごい小さな頃、うちの死んだおじーちゃんの戦友の話をよく聞きました。それと小隊長だった大叔父さんの話もよくききましたねえ)現在でも近隣諸国との軋轢の根本に「情報不足(軽視)」があったのではないかと思ったり・・・。(現在はそこは考え直されてきたようにも感じますが)
。。。。。。。。
井沢元彦の本は目からウロコが多く好きです。でも本当に時々ですが当時としては仕方なかったんじゃないの?と思う感想もあるんですよねえ。。。ちなみにビンボーなので全巻は読んでいませんが、「逆説の日本史」の第一巻「封印された和の謎」はすごいオススメです。多分これだけでいいかも・・・と思ったり(笑)ただちょっと古い本なので、最近の新発見とは微妙にずれる箇所もありますけど(特に邪馬台国論争)
。。。。以下、長いしすごい趣味の分野なので飛ばしておkだと思います。。。。
「逆説の日本史 近世展開編」を読みました。作家の井沢元彦の本には大変影響を受けました。エスカリテ文庫の各宗教の本(「密教の本」とか「神道の本」)を読んで井沢元彦の「世界宗教講座」を読むと「なるほど宗教って」と思います。井沢元彦のライフワークであるという「逆説の日本史」もとびとびで全部は読んでないですけど日本史というものを理解させてくれました。・・・ただ、井沢元彦自身が「荒い捉え方でもあるかもしれない」と言っている通り「むむ?」と思う事もあります。
ビンボーの中、古本屋で「逆説の日本史 近世展開編」を買いました。キリスト教や島原の乱を経ていかに日本が鎖国したかが解き明かされていました。「鎖国法という法はなく日本の鎖国はキリスト教禁令からの成り行きでなし崩しになされたもの」「徳川家康はキリスト教禁令は命じたが、むしろヨーロッパとの貿易には積極的だった」「ゆえに幕末、維新の志士が鎖国はこの国の定法と思っていたのは誤解で家康に従えば開国が本音だった」というのはけっこう目からウロコでした。しかし「このなし崩しの決定は歴史的に観て情報を軽視した江戸幕府(日本)独自の考えでバカだった」というような感じは「むむ?」と思いました。当時の世界の国家で本当に最初から情報をもって計画的に「進出」していた国家ってあったのかいな?ヨーロッパの進出もなんとなく「なし崩し」じゃないのかしらん?比較にそのあたりを出してもらえないと何とも言えないような・・・。ヨーロッパって結果成功してるから「正しかった」ってなってないかしら?とも思うのです。むしろ日本は井沢氏おっしゃるところの「和の精神」に忠実だからこそ「なし崩し」に見えるのではないかなあ?と思ったり・・・。だって大名統制は「由比正雪の乱」までは徹底して変えなかった、と他方では言ってるんだしなんか整合性が・・・と思ったりしました。
しかしこれはつまり日本は「情報に昔から疎い」ということをおっしゃてるのでしょう。もっと言うなら「情報を軽視する」という日本の伝統?があると。これは現代にまで続く日本の欠点、いや弱点だと思います。大東亜戦争でも欧米軍の充分な情報を集めずに中国軍に対するのと同じ戦法で戦い、大きな被害を出したといいます。(ちなみにすごい小さな頃、うちの死んだおじーちゃんの戦友の話をよく聞きました。それと小隊長だった大叔父さんの話もよくききましたねえ)現在でも近隣諸国との軋轢の根本に「情報不足(軽視)」があったのではないかと思ったり・・・。(現在はそこは考え直されてきたようにも感じますが)
。。。。。。。。
井沢元彦の本は目からウロコが多く好きです。でも本当に時々ですが当時としては仕方なかったんじゃないの?と思う感想もあるんですよねえ。。。ちなみにビンボーなので全巻は読んでいませんが、「逆説の日本史」の第一巻「封印された和の謎」はすごいオススメです。多分これだけでいいかも・・・と思ったり(笑)ただちょっと古い本なので、最近の新発見とは微妙にずれる箇所もありますけど(特に邪馬台国論争)
暖かくなって・・・(今回もちと長いです)
最近、お仕事が順調ではありません。悲しいかな載せてもらえる機会もぐっと減ってしまいました。。。ただでさえビンボなのにちょっとつら過ぎます・・・って、暖かくなると何故か体調も精神も不安定になってしまうんですよね。
痩せない・・・と悩んでいましたが、一因かもしれないものがわかりました。現在飲んでいる薬の中に副作用として肥満が現れる場合があるというものが入っているんです。担当医にはあまり替わりのものがないのでもう少し続けようと言われているのですが・・・微妙です。。。
最近歴史関係の本を読んでいて「朱子学」についてちょっと学びました。明治維新の原動力になった水戸学(水戸藩で独自に発展した朱子学)の基本になった教えです。朱子学は儒学の発展系?でしてつまり儒教なんですよね。
儒教といえば現在の縦社会(先輩後輩)の原理でもあり、また「鬼、乱、神を語らず」と言い「神や迷信を否定している」と言うので学問つまり政治学だと捉えられています(だから儒「学」と言うんでしょう)だけど、「天」が「徳」のある天子を選ぶという思想や「天」の意思といういわば絶対神的なものが頂点にありますのでやっぱり儒教(宗教)だと思うんですよねえ。
読んでいて儒教ってちょっと二元論的なとこがあるように感じました。つまり「正義」と「悪」ですね。朱子学で言うと「王者」と「覇者」です。なんか「覇者」って言えばカッコイイですが実は悪い奴なんです。「徳」があってそれによって王になり国を治めるのが「王者」、それに対して武力や力によって無理矢理国をとって王になったのが「覇者」なんです。だから正当な方は「王者」であり「覇者」は本当の王ではないんですよね。朱子学は別名「宋学」とも言い、その名前の通り宋の時代に朱熹(朱子)によって出来ました。宋といえば蒙古(元)によって攻められ、南に追いやられて滅ぼされた王朝。中華(最も文明的な国)を支配するべき漢民族からみれば野蛮なモンゴル人に負けたのが悔しかったんだと思います。だからモンゴルは力で国を取った「覇者」だ、正当なのは「王者」である「宋」だ言う理論をとなえたんじゃないかと・・・。。。
これが日本で水戸学として発展して、徳川幕府は武力によって政権をとった「覇者」、日本の本当の「王者」は天皇だ、となって明治維新になったのです。
儒教によると、この「正義」と「悪」は死んでからもどうやら続くみたいで、死んでからも悪人は悪人。言われてみればそりゃそうだ・・・と思わなくも無いですが、日本人はあまりこうは考えませんでした。例えば平将門。新皇と称し時の朝廷に逆らった大反逆者。普通の国なら当然大悪人ですが、死んだ後には祭られて神になっています。神田明神ですよね。もっと古くは大国主。おそらく出雲王国の王者であって、神話では「国を譲った後、隠れた」となっていますが幽界に行くということは「死んだ」と言う事。大和王朝にとっては敵であった大国主も神となって「天に届くほどの社」に祭られています。日本ではある意味死ねば平等になるんですよね。今でも悪い人だったとしても「死んだ人の悪口はやめよう」「もう死んだのだから」と言ったりします。そういえば京極夏彦の小説でも死んだ殺人者を「荒ぶる神」として祭る描写が出てきましたねえ・・・「魍魎の箱」だったかな??
うちのおじいちゃんは林業を営んでいましたけど今からだと40年位前に山を買いに福島県会津に行った時、トラックの運転手がたまたま山口出身の方でした。それを知ったとたんに今まで愛想よく受け応えていた会津の人が急に無口になり、奥に引っ込んで出てこなくなった・・・という話を聞きました。戊辰戦争の時の白虎隊の悲劇は有名ですが、官軍(長州藩、現在の山口県あたり)は会津兵の死体を「賊軍だから埋葬することはならぬ」として放置させたという話があります。これは中国などではけっこうある話らしいのですが、これも朱子学の影響なんでしょうか。悪人は死んでからも悪人という考えですから悪の兵ということになるのでしょうか・・・・・・(悲)
でも清水の次郎長は官軍のこの命令に逆らって、幕府軍の戦死者を子分を使って皆埋葬したそうです。まさに任侠の親分ですね。。。
でも40年前とはいえ、まだそんな遺恨が残っているものなのかとちょっと信じられませんでした。おじーちゃんが大げさに言ったのかもしれません。よく考えると長州藩は毛利家。毛利家といえば関が原で徳川軍に負けた西軍の総大将(石田光成は19万石なので)。その時家康から「120万石全部を残してあげる」といわれながらだまされて「36万石」にされてしまった家。その遺恨は江戸時代にも残っていたと司馬遼太郎の小説などにも書かれています。遺恨が廻ったということになるのでしょうか。
日本は「怨み」を恐れる文化だと思います。また怨みを残さないよう「水に流す」文化でもあると思います。だから反逆者が神になるいるのではないかと・・・。しかし性善説ではすべてを語れないのは・・・当然なんですよね。。。
と・・・読んだ本から勝手に思いました。思い違いや間違っているかもしれませんが、大目に見てください(汗汗)
痩せない・・・と悩んでいましたが、一因かもしれないものがわかりました。現在飲んでいる薬の中に副作用として肥満が現れる場合があるというものが入っているんです。担当医にはあまり替わりのものがないのでもう少し続けようと言われているのですが・・・微妙です。。。
最近歴史関係の本を読んでいて「朱子学」についてちょっと学びました。明治維新の原動力になった水戸学(水戸藩で独自に発展した朱子学)の基本になった教えです。朱子学は儒学の発展系?でしてつまり儒教なんですよね。
儒教といえば現在の縦社会(先輩後輩)の原理でもあり、また「鬼、乱、神を語らず」と言い「神や迷信を否定している」と言うので学問つまり政治学だと捉えられています(だから儒「学」と言うんでしょう)だけど、「天」が「徳」のある天子を選ぶという思想や「天」の意思といういわば絶対神的なものが頂点にありますのでやっぱり儒教(宗教)だと思うんですよねえ。
読んでいて儒教ってちょっと二元論的なとこがあるように感じました。つまり「正義」と「悪」ですね。朱子学で言うと「王者」と「覇者」です。なんか「覇者」って言えばカッコイイですが実は悪い奴なんです。「徳」があってそれによって王になり国を治めるのが「王者」、それに対して武力や力によって無理矢理国をとって王になったのが「覇者」なんです。だから正当な方は「王者」であり「覇者」は本当の王ではないんですよね。朱子学は別名「宋学」とも言い、その名前の通り宋の時代に朱熹(朱子)によって出来ました。宋といえば蒙古(元)によって攻められ、南に追いやられて滅ぼされた王朝。中華(最も文明的な国)を支配するべき漢民族からみれば野蛮なモンゴル人に負けたのが悔しかったんだと思います。だからモンゴルは力で国を取った「覇者」だ、正当なのは「王者」である「宋」だ言う理論をとなえたんじゃないかと・・・。。。
これが日本で水戸学として発展して、徳川幕府は武力によって政権をとった「覇者」、日本の本当の「王者」は天皇だ、となって明治維新になったのです。
儒教によると、この「正義」と「悪」は死んでからもどうやら続くみたいで、死んでからも悪人は悪人。言われてみればそりゃそうだ・・・と思わなくも無いですが、日本人はあまりこうは考えませんでした。例えば平将門。新皇と称し時の朝廷に逆らった大反逆者。普通の国なら当然大悪人ですが、死んだ後には祭られて神になっています。神田明神ですよね。もっと古くは大国主。おそらく出雲王国の王者であって、神話では「国を譲った後、隠れた」となっていますが幽界に行くということは「死んだ」と言う事。大和王朝にとっては敵であった大国主も神となって「天に届くほどの社」に祭られています。日本ではある意味死ねば平等になるんですよね。今でも悪い人だったとしても「死んだ人の悪口はやめよう」「もう死んだのだから」と言ったりします。そういえば京極夏彦の小説でも死んだ殺人者を「荒ぶる神」として祭る描写が出てきましたねえ・・・「魍魎の箱」だったかな??
うちのおじいちゃんは林業を営んでいましたけど今からだと40年位前に山を買いに福島県会津に行った時、トラックの運転手がたまたま山口出身の方でした。それを知ったとたんに今まで愛想よく受け応えていた会津の人が急に無口になり、奥に引っ込んで出てこなくなった・・・という話を聞きました。戊辰戦争の時の白虎隊の悲劇は有名ですが、官軍(長州藩、現在の山口県あたり)は会津兵の死体を「賊軍だから埋葬することはならぬ」として放置させたという話があります。これは中国などではけっこうある話らしいのですが、これも朱子学の影響なんでしょうか。悪人は死んでからも悪人という考えですから悪の兵ということになるのでしょうか・・・・・・(悲)
でも清水の次郎長は官軍のこの命令に逆らって、幕府軍の戦死者を子分を使って皆埋葬したそうです。まさに任侠の親分ですね。。。
でも40年前とはいえ、まだそんな遺恨が残っているものなのかとちょっと信じられませんでした。おじーちゃんが大げさに言ったのかもしれません。よく考えると長州藩は毛利家。毛利家といえば関が原で徳川軍に負けた西軍の総大将(石田光成は19万石なので)。その時家康から「120万石全部を残してあげる」といわれながらだまされて「36万石」にされてしまった家。その遺恨は江戸時代にも残っていたと司馬遼太郎の小説などにも書かれています。遺恨が廻ったということになるのでしょうか。
日本は「怨み」を恐れる文化だと思います。また怨みを残さないよう「水に流す」文化でもあると思います。だから反逆者が神になるいるのではないかと・・・。しかし性善説ではすべてを語れないのは・・・当然なんですよね。。。
と・・・読んだ本から勝手に思いました。思い違いや間違っているかもしれませんが、大目に見てください(汗汗)